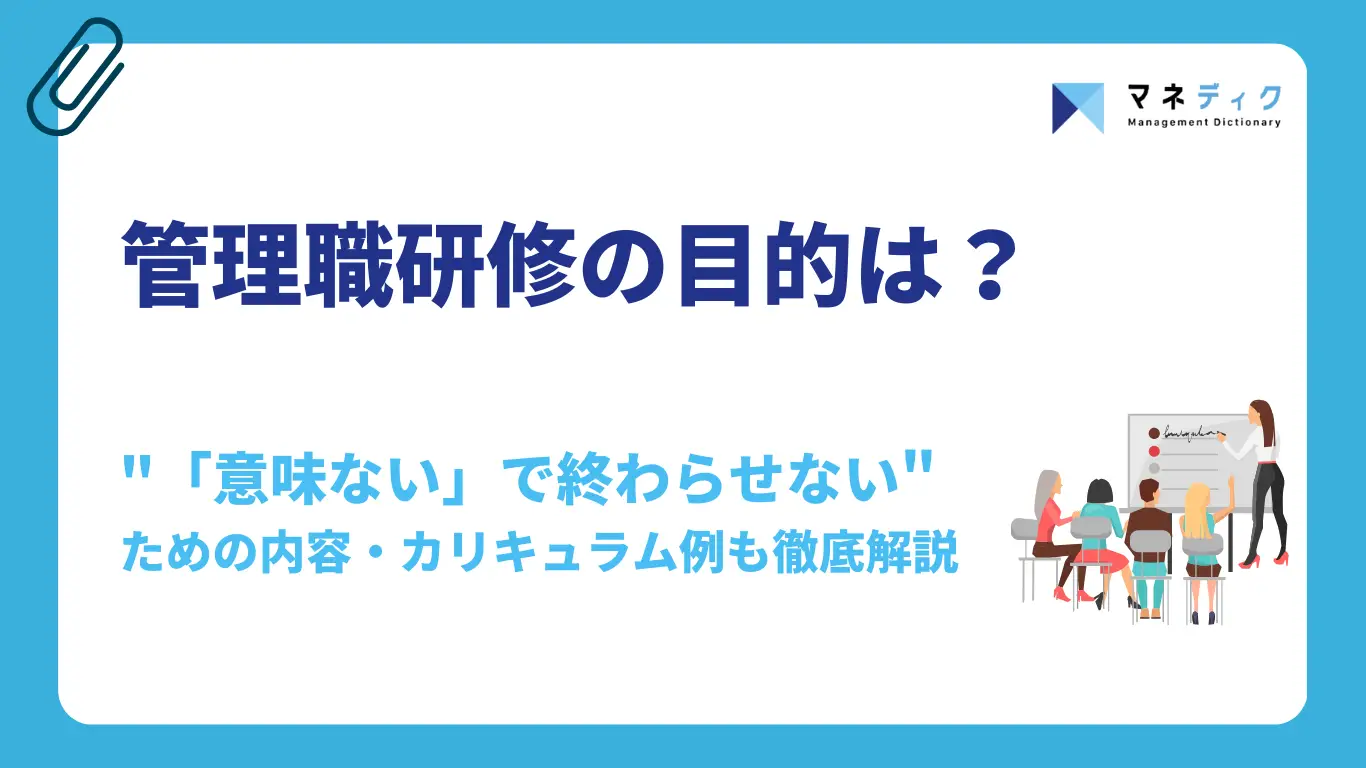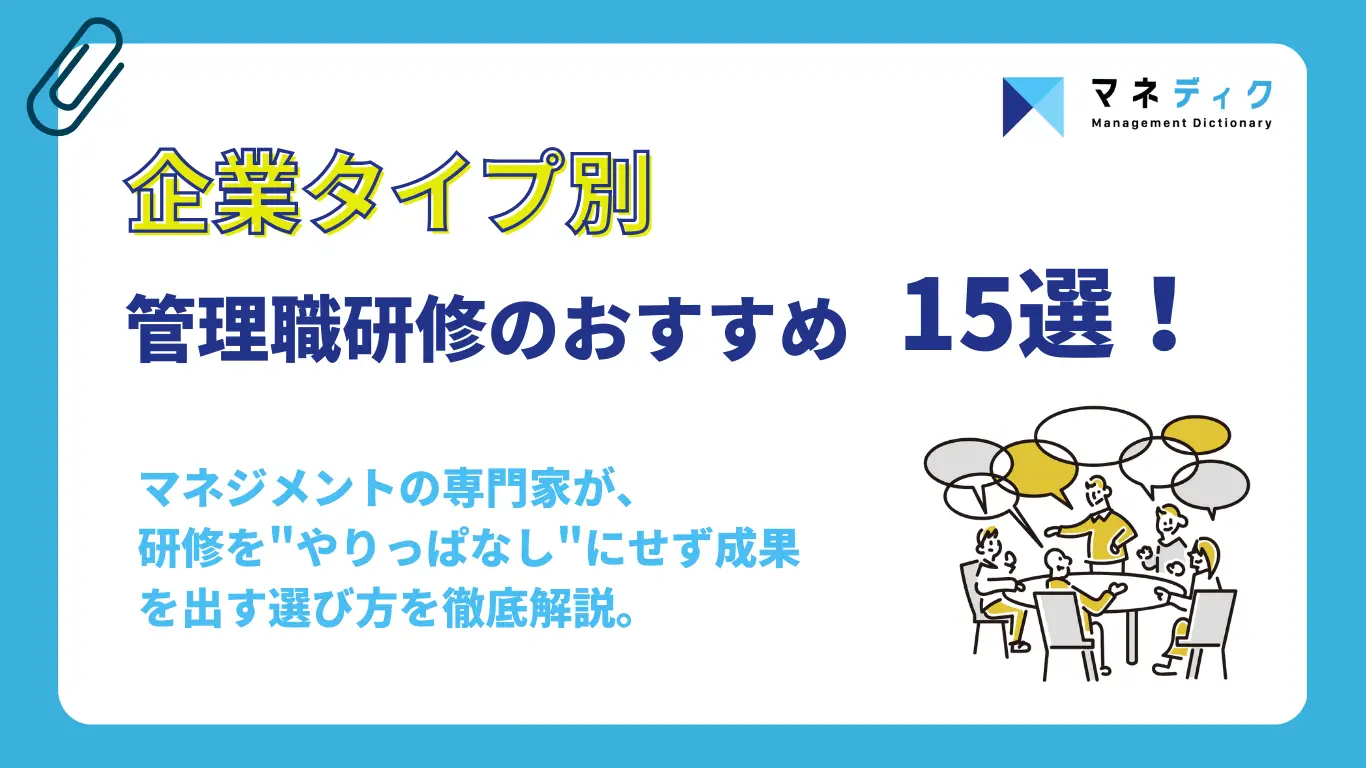MVV浸透ワークショップとは?効果を最大化する設計方法と成功・失敗事例も紹介
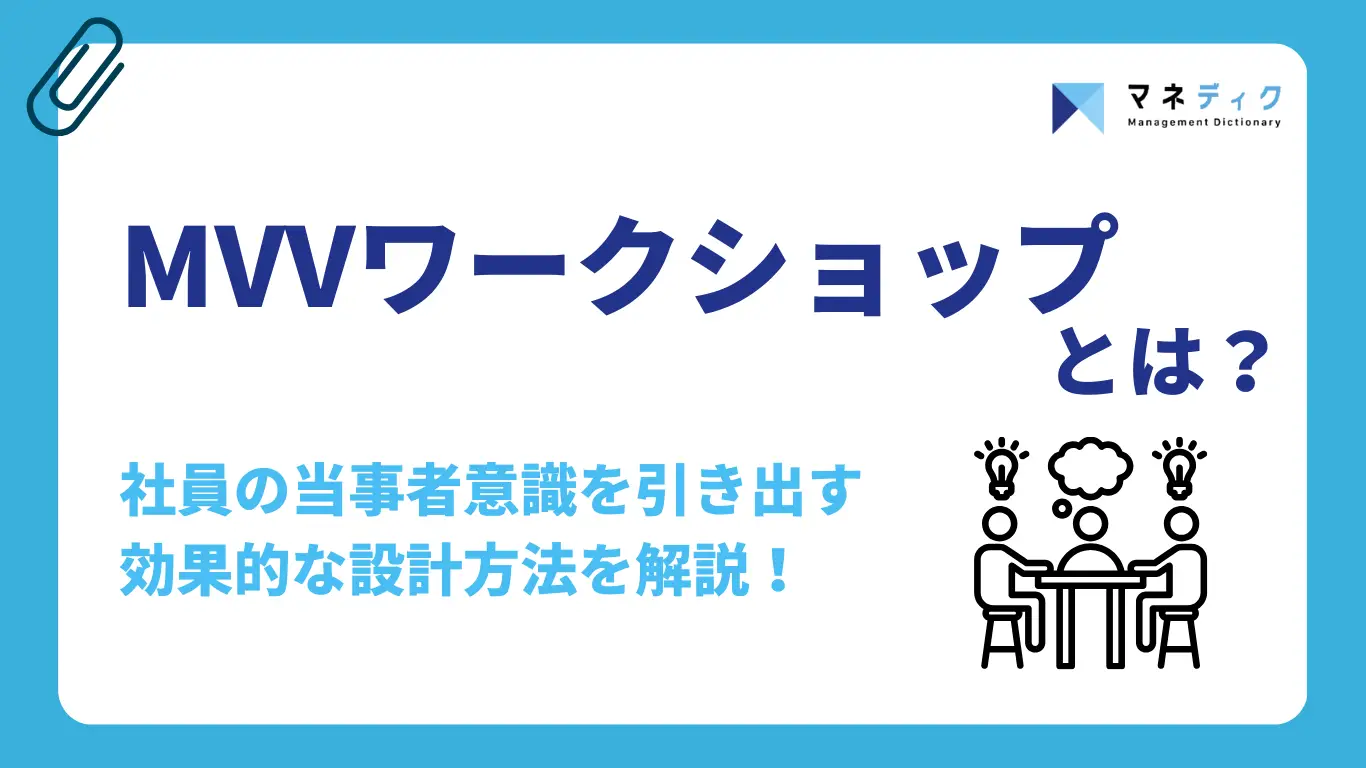
MVV浸透ワークショップとは?
MVV浸透ワークショップとは、単に会社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を知識としてインプットする研修ではありません。
社員一人ひとりが主体的に参加し、対話やグループワークを通じてMVVを「自分たちの言葉」で語り直し、日々の業務と結びつけることで「自分事」として捉えるための参加型プログラムです。
経営層からの一方的な説明や、社内の壁に貼られたポスターを眺めるだけでは、MVVは「会社から与えられたスローガン」のまま響きません。
ワークショップ形式で、社員の内面にある価値観(Will)と会社のMVVとの接点を見つけ出し、同僚とその意味を共有する。この「自分事化」の体験こそが、社員のエンゲージメントを高め、「MVVに基づいた行動」を自律的に生み出すための土台となります。
なぜMVV浸透ワークショップが有用なのか?
そもそも、MVVの浸透施策として、なぜ一方的な説明会ではなく、双方向の「ワークショップ」が有効なのかを以下で詳細に解説します
MVVの"自分事化"が、自律型人材を育てるから
優秀な人材ほど、「なぜこれが必要なのか?」という目的への納得感を重視します。経営陣から一方的に与えられたMVVは「やらされ感」を生み、思考停止を招きます。
ワークショップは、多様なバックグラウンドを持つ社員同士が対話し、MVVを自分たちの言葉で再定義し、日々の業務と結びつける場です。
この「自分事化」のプロセスを通じて、MVVは「会社のルール」から「自分たちの価値観」へと変化し、社員の自律的な行動を後押しします。
"解釈の余白"を共有し、変化への対応力を高めるから
市場環境が目まぐるしく変わる現代において、MVVは厳格なルールブックであってはなりません。むしろ、予測不能な事態に直面した際に、社員が自ら考えて行動するための「拠り所」になるべきです。
ワークショップは、具体的な業務シーンを題材に「このバリューに基づけば、どう判断すべきか?」を擬似体験させる絶好の機会です。
様々なケースでMVVの「解釈」をシミュレーションすることで、現場での応用力が養われ、組織全体として変化に強い柔軟性が生まれます。
心理的安全性を醸成し、カルチャーの土台を築くから
特にベンチャーや急成長する組織では、意図的にカルチャーを形成しなければ、容易に一体感が失われます。
MVVについて本音で語り合うワークショップは、健全な意見対立を歓迎し、互いの価値観を尊重する文化、すなわち「心理的安全性」を醸成する効果があります。
MVVという共通のテーマについて対話することは、単なる浸透施策に留まらず、風通しの良い組織文化を創るための重要なプロセスになります。
【失敗事例】MVV浸透ワークショップが陥りがちな3つの罠
良かれと思って企画したワークショップが、なぜかうまくいかない。それには共通する「罠」があります。以下でそれぞれ陥りがちな罠をご紹介するので、自社が陥りがちなパターンがないか、チェックしてみてください。
罠1:経営層の「他人事」感と現場の温度差
最も多い失敗が、経営層のコミットメント不足です。
「MVVは大事だ」と言いながら、ワークショップの場には顔を出さず、現場に丸投げ。これでは、社員は「どうせ経営層は本気じゃない」と敏感に察知し、施策全体が白けてしまいます。経営層自らがMVVを体現し、その重要性を自分の言葉で語り続ける姿勢が、浸透の絶対条件です。
罠2:抽象的で「自分事」にできないMVV
陥りがちな罠の2つ目が、MVVが抽象的すぎて「自分事」化できないケースです。
「世界を笑顔に」「社会に貢献する」といったMVVは、立派ではあるものの、抽象的すぎて現場の社員は自分の業務とどう繋がるのかイメージできません。
「このバリューは、日々の営業活動でいうと、具体的にどういう行動を指すのか?」まで翻訳され、具体的な行動指針に落とし込まれていないMVVは、浸透のしようがありません。
罠3:一過性のイベントで終わってしまう
陥りがちな罠の3つ目が、MVVワークショップが一過性のイベントで終わってしまうケースです。
ワークショップ当日は大いに盛り上がり、「良い話が聞けた」と参加者も満足。しかし、翌日からは元の日常に戻り、何も変わらない。
これは、ワークショップで生まれた熱量を、日々の業務における行動変容へと繋げる「仕組み」が設計されていないために起こります。研修はあくまでスタート地点であり、その後の実践と振り返りのサイクルこそが重要なのです。
MVV浸透ワークショップの進め方【5ステップ】
では、具体的にどのようにワークショップを企画し、実行すればよいでしょうか?
ここでは、MVVワークショップを成功に導き、継続的な事業成長に繋げるための5つのステップを解説します。
ステップ1:目的とゴール設定を入念に行う
まず、「このワークショップを通じて、参加者にどうなってほしいのか」という目的とゴールを明確に言語化します。
例えば、「MVVを暗唱できるようになる」のはゴールではありません。
「自部門の課題をMVVと結びつけて語れるようになる」「バリューを体現する行動目標を一人ひとりが設定する」といった、超具体的な行動レベルでのゴールを設定することが重要です。
ステップ2:参加者の当事者意識を醸成する事前課題
MVVワークショップを「受け身」で参加させないために、事前課題を用意することは非常に有効です。
例えば、以下のような問いを投げかけ、当日までに自分の考えをまとめてきてもらいましょう。
あなたが仕事で「これは価値ある仕事だ」と感じた瞬間は、どんな時でしたか?
会社のMVVの中で、あなたが最も共感する(あるいは、違和感を持つ)ものはどれですか?その理由は?
あなたのチームが、MVVを最も体現できている点は何だと思いますか?逆に、課題は何ですか?
ステップ3:【事例で学ぶ】MVVを「自分事化」する2つのプログラム
ワークショップの核となるプログラムです。
ここでは、参加者が「自分事」としてMVVを捉えるための、具体的なワークを3つ紹介します。
プログラム例①:個人の価値観と会社のバリューを紐付けるワーク
個人の価値観(Will)と会社の価値観(Value)の重なりを見つけるワークです。 「あなたが人生で大切にしていることは何か?」を参加者同士で共有し、それが会社のどのバリューと繋がっているかを探求します。これにより、会社への貢献が自己実現にも繋がるという感覚を醸成します。
プログラム例②:日々の業務とミッションの繋がりを見出すワーク
「"このタスクをやる意味は?"という問いに、自分自身で答えを見つける」ためのワークです。 参加者の実際の業務内容を題材に、「その仕事は、最終的に我々のミッションのどの部分に繋がっているか?」をグループで議論します。日々の業務に追われる中で見失いがちな「目的」を再発見してもらいます。
ステップ4:ネクストアクションと実践の仕組み化
ワークショップの最後には、必ず具体的な「次の行動」を決めます。正直ワークショップ後のアクションを明確にしているか、ワークショップ後の実践の仕組み化ができているかどうかが効果的なワークショップになるかどうかを決めているといっても過言ではありません。
「明日から、MVVを意識して〇〇という行動を始めます」といった個人目標の設定や、チーム単位でのアクションプラン策定を促しましょう。
そして、その実践を支援し、定着させるための「仕組み」を提示することが重要です。例えば、週報に「今週のバリュー実践報告」の欄を設けたり、1on1で進捗を確認したりといった、日常業務に組み込む工夫が求められます。
ステップ5:効果を測定し、改善サイクルを回す
ワークショップはやりっぱなしでは意味がありません。
施策の効果を客観的に測定し、改善していく視点が不可欠です。
例えば、実施前後でエンゲージメントサーベイのスコアがどう変化したか、MVVに関する社内アンケートの結果はどうだったか、といったデータを定点観測しましょう。これらのデータに基づき、次の施策を改善していくPDCAサイクルを回すことで、MVV浸透は一過性のイベントではなく、継続的な組織開発活動に変わります。
ここではMVV浸透ワークショップの効果的な進め方を解説させていただきましたが、ワークショップをおこなううえでは「どのようなテーマを選定するか?」と同じくらい「どのように運営するか?」が重要です。実際の参加者満足度やその後のMVV浸透度にも大きく影響する部分です。
特にベンチャー企業や急成長企業だと、ワークショップを自社内で企画・運営する余裕がないのが実態かと思います。
我々マネディクは、これまで300社以上を超えるベンチャー/成長企業様にマネジメント研修のご提供やワークショップのご支援をさせていただいた経験から、変化の激しいベンチャー/成長企業の環境・状況に合わせたサービス・ワークショップのご提供が可能です。
貴社の現状の課題に即したカスタマイズワークショップをご提供させていただきます。
少しでもご興味を持っていただきましたら、以下からサービス資料を無料ダウンロードできますので、お気軽にご覧ください。

ワークショップの成否を分ける!ファシリテーターの役割と心得
効果的なMVVワークショップの実現には、議論を活性化させ、参加者の本音を引き出す「ファシリテーター」の存在が欠かせません。
ここでは、ワークショップのファシリテーターに求められる役割と心得について解説していきます。
参加者の本音を引き出す「問いかけ」の技術
優れたファシリテーターは、答えを教えるのではなく、良質な「問い」を投げかけます。
「なぜそう思うのですか?」「具体的にはどういうことですか?」「もし〇〇だとしたら、どうしますか?」といった問いを通じて、参加者の思考を深掘りし、対話を活性化させます。
特に、普段は発言しにくいメンバーにも話を振るなど、全員が参加できる場作りが重要です。
意見が対立した時の場の収め方
MVVについて本音で語り合えば、当然、意見の対立も起こり得ます。
ファシリテーターは、それを問題と捉えるのではなく、組織が健全である証拠と歓迎すべきです。
どちらが正しいかをジャッジするのではなく、「Aさんは〇〇という視点ですね」「Bさんは△△を懸念しているのですね」と双方の意見を受け止め、共通のゴール(MVVの実現)に向けて、どうすれば両者の視点を統合できるか、という建設的な議論へと導く役割が求められます。
進行役は外部に頼むべき?社内で行うべき?
「ワークショップのファシリテーターは外部の方に頼むべき?」との声をよくいただきますが、外部のプロに依頼すれば、質の高い進行が期待できます。
一方で、毎回外部に依存していては、コストがかさむだけでなく、社内にノウハウが蓄積されません。 理想は、初回は外部のプロの力を借りつつ、将来的には人事担当者やマネージャーがファシリテーターを務められるよう、「自走化」を目指すことです。
こうしたワークショップのファシリテーターはファシリテーション力に加えて、MVV浸透やカルチャー、組織開発に精通していることが求められるので、より効果的なワークショップ・研修をおこなうのであれば初期は外部のプロに入ってもらうことをおすすめします。
MVV浸透ワークショップに関するよくある質問
Q. ワークショップの時間はどのくらいが適切ですか?
A. 目的や内容によりますが、半日(3〜4時間)から1日(6〜7時間)かけて実施するケースが一般的です。重要なのは、十分な対話の時間を確保することです。
Q. オンラインでも実施可能ですか?
A. はい、可能です。
オンラインツール(ブレイクアウトルーム機能など)を活用すれば、オンラインでも効果的なワークショップは実施できます。ただし、オフラインに比べて一体感が醸成しにくい側面もあるため、アイスブレイクを多めに取り入れるなどの工夫が必要です。
Q. 参加者のモチベーションを上げるにはどうすればいいですか?
A. 「なぜこのワークショップを行うのか」という目的を、経営層が自分の言葉で熱意をもって語ることが最も重要です。
また、ワークショップの内容が、参加者自身の悩みや課題解決に直結するものであることを丁寧に説明し、「自分にとって有益な時間だ」と感じてもらうことが大切です。
Q. VMVとMVVの違いは何ですか?
A. 基本的に同じものを指しますが、提唱者や企業によって順番が異なることがあります。
重要なのは言葉の順番ではなく、ミッション(M)、ビジョン(V)、バリュー(V)の3つが、それぞれ企業の「存在意義」「目指す姿」「行動指針」として明確に定義され、連動していることです。
Q. ワークショップの費用感はどのくらいですか?
A. 外部に委託する場合、講師のレベルやプログラムの内容、参加人数によって大きく変動しますが、数十万円から数百万円かかるケースが一般的です。
社内でファシリテーターを育成し、内製化(自走化)することで、長期的なコストを抑えつつ、組織にノウハウを蓄積することが可能になります。