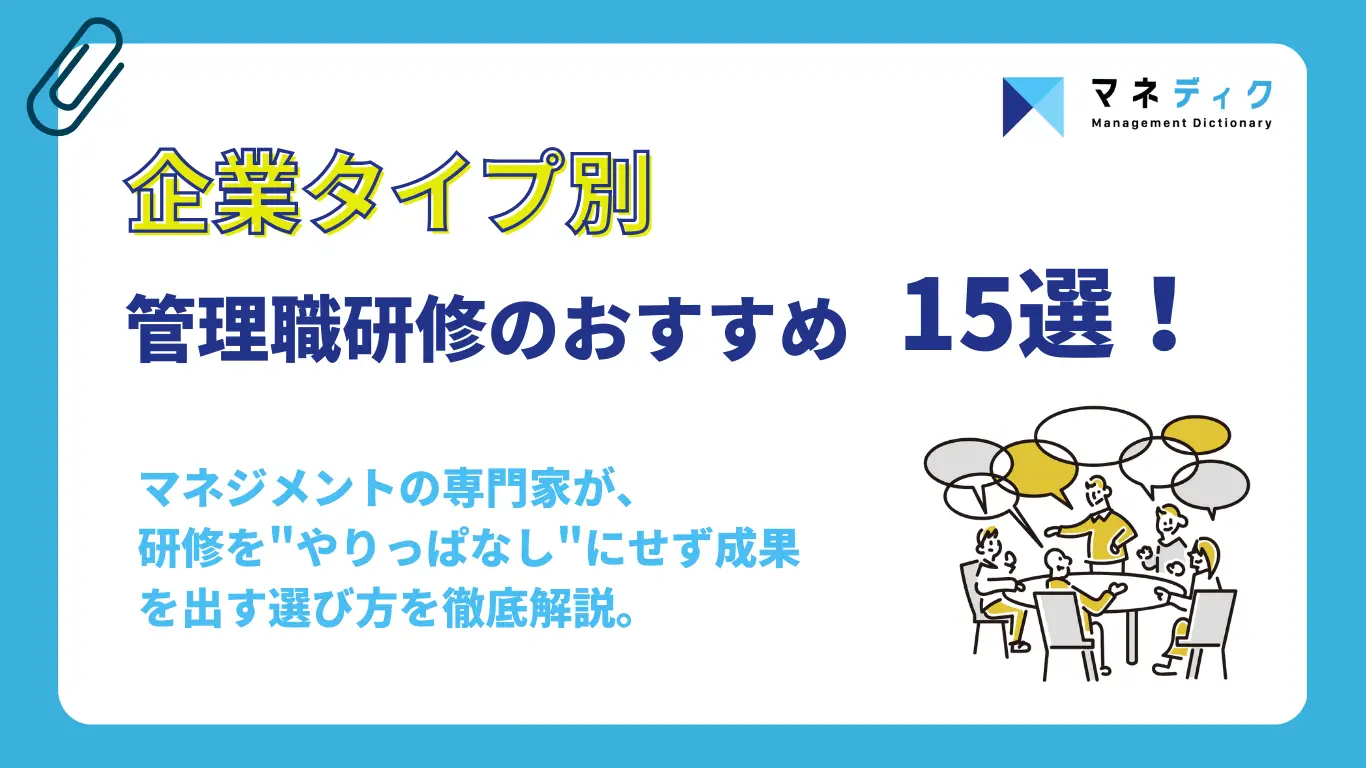管理職研修の目的とは?「意味ない」で終わらせないための内容・カリキュラム例を徹底解説
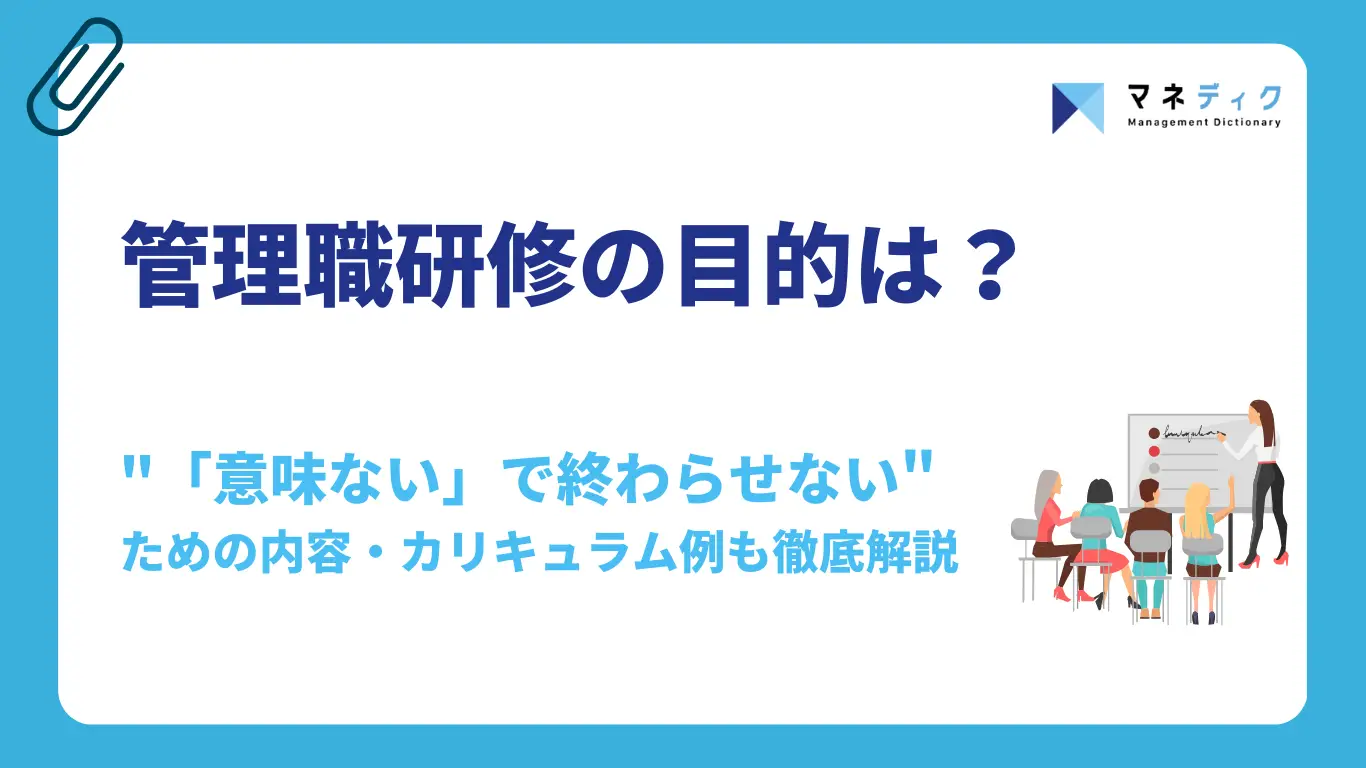
なぜ管理職研修は「意味ない」と言われるのか?
多くの企業で良かれと思って実施される管理職研修が、なぜ現場の管理職や経営者から「意味がない」と断じられてしまうのか。
その背景には、多くの研修が陥りがちな3つの共通した課題があります。
以下で「管理職研修は意味ない」と言われる理由を3つそれぞれご紹介していきます。
理由1:研修内容が一般論で、現場の課題と乖離している
1つ目の理由は、研修内容が抽象的な理論や一般論に終始し、自社が直面している生々しい課題の解決に直結しない、もしくは直結しないと感じられてしまうことです。
例えば、「部下のモチベーションを高める方法」として心理学のフレームワークを学んだとしても、自社の評価制度やカルチャー、事業の特性といった固有の文脈を無視した内容では、現場のマネージャーは「理論としてはわかるが、実際の現場では使えない」と感じてしまいます。
特に、日々変化する市場環境の中で成果を求められるベンチャー/成長企業の管理職にとって、自社の「今、ここ」にある課題と結びつかない知識は、単なるお勉強で終わってしまいます。
そのため、管理職研修を実際におこなう場合は、一般的なマネジメント論や抽象的・汎用的なものだけに終始するプログラムではなく、現状の組織課題や現場の状況、組織が目指す方向に即した研修をおこなわないと意味がありません。
外部の管理職研修を検討される際も、ただの座学や理論に終始するものではなく、「各企業に合わせた実践的な研修プログラムを組んでくれるか」という観点で見極めることをおすすめします。
理由2:一過性のイベントで終わり、行動変容に繋がらない
2つ目の理由は、研修が単発の「イベント」として扱われ、学んだ内容を現場で実践し、定着させるまでの仕組みが設計されていないことです。
研修当日にどれだけモチベーションが上がっても、翌日から通常業務に戻れば、学んだことを意識する余裕はすぐになくなります。研修で学んだ新しいマネジメント理論・手法を試そうとしても、日々の業務に追われ、結局は元のやり方に戻ってしまう。
このような「やりっぱなし」の状態では、受講した管理職の方の行動変容は期待できません。そのため研修は、知識をインプットする「点」の施策ではなく、行動変容を促し続ける「線」の仕組みとしてデザインされる必要があります。
また3つ目の理由と通ずる部分もありますが、受講する管理職の方々自身が「この研修は本当に意味があるのか?」と感じている状態で受講した内容が行動変容に繋がることは断じてありません。
研修を単発で終わらせないために、研修の前後にフォローアップの仕組みを組み込みましょう。 例えば、研修前に上司と管理職当人が課題と目標をすり合わせ、研修後には定期的な面談や実践報告会を開き、行動変容を組織として継続的に支援するプロセスを設計することが有効です。
理由3:受講者である管理職自身が目的を理解していない
3つ目の理由は、研修に参加する管理職自身が「なぜこの研修を受けるのか」という目的を自分事として理解・納得していないケースです。
会社から「受けるように」と指示されただけの研修では、受講者はどうしても受け身の姿勢になります。
「これは自分のため、そしてチームのために必要な学びだ」という当事者意識がなければ、研修内容は右から左へと受け流されてしまいます。受け流された研修の内容は何の行動変容も起こさず、結果「管理職研修は意味がなかった」と言われてしまいます。
研修の効果を最大化するためには、経営層から研修の意図や期待を直接伝えたり、直属の上司が本人の課題と結びつけて受講を促したりすることで、やらされ感を払拭することが重要です。また、本人の意見を実際の研修内容に反映させることも、主体的な参加を促す上では効果的です。
管理職研修の本当の目的とは?
では、「意味のある」管理職研修にするために、その目的をどう捉え直すべきなのか?
管理職研修の目的は、単なる個別のマネジメントスキルを習得させることではありません。変化の激しい現代において、管理職研修が果たすべき本当の目的は、以下の3つに集約されます。
特にベンチャー企業や急成長企業においては、研修にかけられる費用や時間が限られているため、以下の目的を抑えたうえで研修を受けられるかどうかが、その後の事業成長を左右してしまいます。こちらを念頭においたうえでご覧ください。
目的1:管理職は経営と現場を繋ぐ超重要な役割だと理解する
管理職研修の目的の1つ目は、管理職が経営と現場を繋ぐ超重要な役割だと理解することです。
管理職は、経営陣が示すビジョンや戦略を現場に浸透させ、同時に現場で起きている課題や生の情報を経営にフィードバックするという、事業成長において非常に重要な役割を担います。
研修の目的は、この管理職としての真の役割を実際の管理職の方々が深く認識し、会社の「背骨」として機能するための視座と覚悟を身につけてもらうことです。
経営と現場、双方の主張を理解し、翻訳しながら組織を動かしていく。この役割を定義して、全管理職が共通認識を持つことこそが、管理職研修の大きな目的の1つです。
目的2:組織共通の「行動様式(カルチャー)」をインストールする
管理職研修の目的の2つ目は、管理職に組織共通の「行動様式(カルチャー)」をインストールすることです。
企業の急速な事業成長、そしてその後の持続的な成長を支えるのは、マニュアルではなくカルチャーです。
カルチャーとは、「こういう場面では、こう考え、こう動く」というある種の行動様式のようなもので、カルチャーが浸透している状態とは組織の全員がある共通の行動様式を実現できている状態です。
管理職研修の最も重要な目的の一つは、この組織の基盤となる行動様式(カルチャー)を、全管理職にインストールすることです。
管理職の言動は、各チームの文化を直接的に形成します。研修を通じて、自社のカルチャーを組織の中枢を担う管理職にインストールすることで、組織全体に一貫したカルチャーが浸透していきます。
目的3:次世代の経営幹部候補を選抜・育成する
管理職研修は、将来の会社を担う経営幹部候補を発掘し、育成するための重要な機会でもあります。
研修での議論や課題への取り組み姿勢を通じて、参加者のポテンシャルや経営視点の有無を見極めることができます。
現場のマネジメントに留まらず、全社最適の視点で物事を考え、事業を動かしていける人材を見出し、早期から戦略的な育成機会を提供していく。これは、企業の未来を創るためのサクセッションプラン(後継者育成計画)そのものです。
【階層別】目的を達成する管理職研修の必須内容とカリキュラム例
先程ご紹介した管理職研修の本当の目的を達成するためには、管理職の階層(役職)に応じて、研修の内容を最適化する必要があります。ここでは、それぞれの階層で求められる役割と、それに紐づく研修内容の例をご紹介します。
ただ、各企業のフェーズ・状況、目指すべき方向によって管理職研修に必要な内容やカリキュラムも変わってくるので、あくまで汎用的な内容であることはご了承ください。
【新任管理職向け】プレイヤーからの脱却と基本スキルの習得
初めて部下を持つ新任管理職、プレイングマネージャー、チームリーダーが最初に直面する壁は、「ハイプレイヤー」からの意識変革です。
自ら手を動かして成果を出すことから、チームメンバーを動かして成果を出すことへ。この役割転換を促すことが新任管理職研修の最大の目的です。
【必須内容・カリキュラム例】
- 管理職の役割認識(プレイヤーとの違い)
- 労務管理の基礎知識(勤怠管理、ハラスメント防止)
- 目標設定と進捗管理(PDCAサイクルの回し方)
- 部下とのコミュニケーション(1on1、フィードバックの基本)
- チームビルディングの基礎
【中間管理職向け】組織の中核としてチームの成果を最大化する
中間管理職、マネージャー、事業責任者は、担当部署の目標達成に責任を持つと同時に、経営と現場の橋渡し役も担う、組織運営の中核です。より高度なマネジメントスキルを駆使しながら、チームのパフォーマンスを最大化することが求められます。
【必須内容・カリキュラム例】
- リーダーシップの発揮(ビジョン浸透、動機付け)
- 問題解決と思考法(ロジカルシンキング、課題設定)
- コーチングスキル(部下の主体性を引き出す)
- 人事評価とフィードバック面談
- 部門間調整・ネゴシエーション
【上級管理職向け】経営視点を持ち、事業と組織の変革を牽引する
部長職以上の上級管理職(主に事業部長やCxOクラスの役職者)には、一事業部門の責任者という立場を超え、経営者と同じ視座で全社的な戦略を考え、事業や組織の変革をリードしていく役割が期待されます。
【必須内容・カリキュラム例】
- 経営戦略と事業計画の策定
- 組織開発とチェンジマネジメント
- 財務会計の基礎知識(PL/BS/CF)
- リスクマネジメント
- 次世代リーダーの育成とサクセッションプラン
カルチャーを醸成するためのワークショップ事例
前述の「組織共通の行動様式(カルチャー)をインストールする」という目的を達成するためには、座学による研修だけでなく、参加する管理職同士が実際に対話し、自社の文脈に落とし込むカルチャーワークショップも極めて有効です。
ワークショップ例:「わが社における『当事者意識』とは何か?」 | |
| インプット | まず、「当事者意識」の一般的な定義や、それが欠如した場合に起こる問題(指示待ち、責任転嫁など)を学習。 |
| 個人ワーク | 参加者一人ひとりが、過去に「当事者意識が高い」と感じた自社のメンバーの具体的な行動を書き出す。 |
| グループディスカッション | グループに分かれ、「なぜその行動が当事者意識が高いと言えるのか」「自部署でその行動を増やすにはどうすれば良いか」を徹底的に議論し、言語化。 |
| 発表・共有 | 各グループの議論の結果を発表し、会社として推奨すべき「当事者意識の高い行動」の解像度を、全管理職ですり合わせます。 |
このようなワークショップを通じて、抽象的なバリュー・理念が具体的な行動レベルに翻訳され、現場での共通言語として浸透していきます。
管理職研修の投資対効果(ROI)をどう測るか?
経営者の視点から見れば、研修はコストではなく「投資」です。そして、投資である以上、そのリターン(効果)を測定し、事業成果との関連性を測ることが必須です。
効果測定で見るべき4つのレベル
研修の効果測定には、ドナルド・カークパトリックが提唱した「4段階評価モデル」がよく用いられます。
- ドナルド・カークパトリックの「4段階評価モデル」とは・・・
- 研修や教育プログラムの効果を測定・評価するための世界的に広く利用されているフレームワーク。研修の成果を4つの異なるレベルで段階的に評価することにより、単なる受講者の満足度だけでなく、最終的なビジネスへの貢献度までを可視化することを目的としている。
| レベル1:反応 | 研修直後の満足度を測定。「研修内容は有益でしたか?」といった研修後アンケートなどがこれに該当。 |
| レベル2:学習 | 知識やスキルの習得度を測定。理解度テストやレポート提出などで評価。 |
| レベル3:行動 | 研修で学んだことが、現場の行動に変化として現れているかを評価。上司や部下への360度評価や、前述のSaaSツールでの実践度チェックが有効。 |
| レベル4:結果 | 行動変容が、最終的に組織や事業の成果にどのような影響を与えたかを測定。これが最も重要かつ測定が難しい指標。 |
離職率や生産性などのKGIへのインパクト事例
管理職研修において、レベル4の「結果」を測定するには、研修の目的と事業上の重要業績評価指標(KGI)を予め紐づけておくことが重要です。
例えば、「部下とのコミュニケーション」に関する管理職研修を実施した場合、そのインパクトは以下のようなKGIの変化として現れる可能性があります。
- エンゲージメントスコアの向上
- 研修後、定期的に実施するエンゲージメントサーベイの「上司との関係」といった項目のスコアが向上。
- 離職率の低下
- 優秀人材(キーマン)や若手社員の離職率が低下。
- チームの生産性向上
- 目標達成率や、プロジェクトの納期遵守率が改善。
実際に、あるベンチャー企業では、管理職研修を導入した結果、エンゲージメントスコアが19ポイント向上し、新商品の目標達成率が40%から95%へと劇的に改善したという事例もあります。
研修を事業成果と結びつけて評価することこそが、戦略的投資としての価値を証明する鍵となります。
管理職研修に関するよくある質問
Q1.中小企業でも管理職研修は実施すべきですか?
A.はい、むしろリソースが限られる中小企業こそ、事業成長の鍵を握る管理職の育成が不可欠です。
一人の管理職が組織全体に与える影響が大きいからです。大規模な研修でなくとも、まずは経営者が自ら講師となり、自社の価値観やマネジメント方針を共有する場を設けることから始めるのが有効です。
ただ第三者として、組織開発・マネジメントのプロが仲介したほうがより管理職やメンバーに経営者の想いや価値観が伝達しやすかったりもするので、思い切って外部の管理職研修を導入してみるのもおすすめです。
Q2.オンラインとオフライン(集合研修)、どちらが効果的ですか?
A.一概にどちらが良いとは言えません。
知識のインプットは場所を選ばないオンライン(eラーニング)が効率的であり、参加者同士の議論や関係構築を目的とするワークショップはオフライン(集合研修)が適しています。
それぞれのメリットを組み合わせた「ブレンディッドラーニング」が近年の主流です。
- 「ブレンディッドラーニング」とは?・・・
- 複数の学習方法を最適に組み合わせることで、学習効果の最大化を目指す教育・学習の手法のこと。具体的には、集合研修(対面での学習)やeラーニング(オンライン学習)といった異なる形式の学びを「ブレンド(混ぜ合わせる)」することが一般的です。それぞれの学習方法が持つ長所を活かし、短所を補い合うことで、一方的な学習方法だけでは得られない高い効果が期待できる。
結局は、管理職研修が単なるインプットや学習の場で終わらないことが重要です。
座学やeラーニングのような動画教材でマネジメントや戦略立案などの管理職に必要なスキルや考え方をインプットし、ワークショップやディスカッションのような場でアウトプットし、学習した内容が実践できているか(もしくは学習した内容が実際の現場で本当に活きるのか)を確認する、このサイクルが確立されていればオンラインでもオフラインでも問題ありません。
あとは今の組織状況や持っている課題に合わせて、研修のスタイルを選択することが大切です。
アウトプットの機会は多分にあるが、圧倒的にマネジメントの一般論や知識が不足していることが課題であれば動画教材や座学のみでも構いませんし、逆にインプットは十分にできているが自社の状況に合わせたアウトプットができていない状況であればワークショップや実践的な研修が効果的です。
企業によって状況や課題感は様々かと思いますが、特に変動性が高いベンチャー・成長企業ではインプット→アウトプットを高速で回して、自社に即したマネジメント体制やカルチャー基盤をいち早く作ることが何より重要です。
我々マネディクでは、そんな急速な事業成長を目指すベンチャー企業向けにマネジメント学習ができるSaaSツールからそれを自社に落とし込むセッションやワークショップまで一貫してご提供させていただいております。
外部の研修やサービスに頼り続けるのではなく、最終的には自社内でマネジメント研修や人材育成、カルチャー形成ができることをゴールに伴走型のご支援をさせていただいております。
「継続的な効果が見込める研修や変動性が高い環境に適した実践的な研修が受けたい」「自社特有のマネジメント基盤やカルチャーを形成して、外部研修に頼り続けない組織づくりに興味がある」といったベンチャーの経営者・役職者の方は、ぜひ一度以下からサービス資料の無料ダウンロードをお願いいたします。