【2025年版】管理職研修のおすすめ全15選!企業タイプ別に適した選び方を専門家が徹底解説
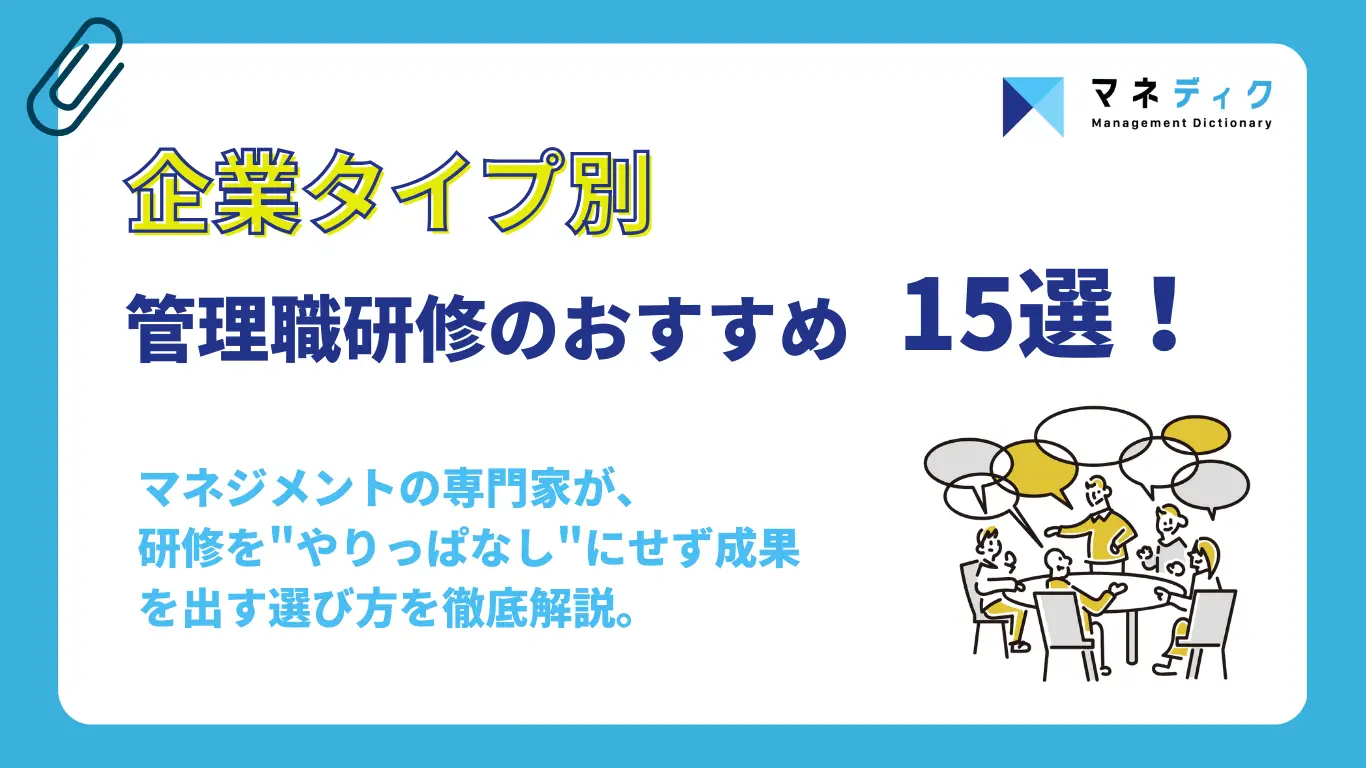
【企業タイプ別】おすすめの管理職研修サービス全15選!
マネジメント研修は数多く存在し、一体どれを選べば良いか分からない、という声をよくお聞きします。そこで本章では、まず企業タイプ別におすすめできる代表的な管理職研修サービスをご紹介します。
【大企業向け】おすすめの管理職研修 5選
大企業では、硬直化した組織を動かし、イノベーションを生み出すことを目的とした、体系的で大規模なプログラムが選ばれる傾向にあります。
成熟した組織では、既存の事業やルールが安定している一方で、前例踏襲や部門最適化が進行しやすいという課題が考えられます。そのため、管理職には現状維持ではなく、組織に新たな変化をもたらし、変革をリードする役割が期待されることが多いです。
研修内容としては、部下の挑戦を促すための「ビジョン構想力」や、多様な人材を巻き込む「エンゲージメント向上」といったテーマが重視される傾向が見られます。実績のある大手研修会社では、アセスメントと連動した客観的なプログラムが充実している点も特徴といえるでしょう。
運営会社 |  株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ |  株式会社グロービス 株式会社グロービス |  株式会社リンクアンドモチベーション 株式会社リンクアンドモチベーション |  アルー株式会社 アルー株式会社 |  一般社団法人日本能率協会(JMA) 一般社団法人日本能率協会(JMA) |
|---|---|---|---|---|---|
対象者 | ローワーマネジメント ミドルマネジメント | ミドルマネジメント トップマネジメント | ミドルマネジメント トップマネジメント | ローワーマネジメント ミドルマネジメント | ローワーマネジメント ミドルマネジメント トップマネジメント |
導入企業例 | ・株式会社ヤクルト ・東京電設サービス株式会社 ・株式会社NexTone | ・パーソルテンプスタッフ株式会社 ・清水建設株式会社 ・株式会社ユナイテッドアローズ | ・イオン株式会社 ・東武鉄道株式会社 ・株式会社西武ホールディングス | ・ANA成田エアポートサービス株式会社 ・TOPPAN株式会社 ・日東電工株式会社 | ・株式会社ゼンリン ・株式会社日税ホールディングス ・株式会社マインズ |
料金体系 | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり | 公開講座:5万円/人〜 |

【内容】
リクルートマネジメントソリューションズの管理職研修は、30年以上にわたる豊富な実績と科学的根拠に基づき、「メンバーの成長」と「組織の成果」を両立できる管理職の育成を目指します。研修では、マネジメントの原理原則の学習と実践演習を繰り返し、現場で確実に成果を出せるリーダーシップとマネジメント能力を体系的に習得します。
【特徴】
特徴は、個人の強みや課題を可視化するアセスメントを組み合わせられる点です。客観的なデータに基づいて自己認識を深め、一人ひとりの課題に合わせた具体的なアクションプランを描くことで、効果的な成長を促します。研修後の実践支援ツールも豊富で、学びの定着まで一貫してサポートします。
【このような企業におすすめ】
- 次世代の経営幹部を、客観的なデータに基づいて選抜・育成したい
プレイヤーからマネージャーへの意識変革に課題を感じている
現場の課題解決をリードし、組織目標を達成できる管理職を育てたい
▶︎資料ダウンロードはこちら
2. 株式会社グロービス

【内容】
グロービスの管理職研修は、経営大学院の知見を活かし、管理職に「経営者視点」を醸成することに主眼を置いています。ヒト・モノ・カネといった経営資源の全体像を理解し、論理的思考力や問題解決能力を徹底的に鍛えることで、組織の変革を推進できるリーダーを育成します。
【特徴】
ケーススタディを用いた討議中心の実践的なプログラムが特徴です。実際の企業事例を元に、当事者として意思決定を行う経験を積むことで、答えのない課題に取り組む思考力を養います。オンライン学習プラットフォーム「GLOBIS 学び放題」と組み合わせることで、知識のインプットと実践を効率的に行き来できる点も強みです。
【このような企業におすすめ】
- 部分最適ではなく、全社的な視点を持った管理職を育成したい
VUCA時代に対応できる、戦略的思考力や意思決定力を強化したい
次世代の経営幹部候補を早期から選抜・育成したい
▶︎資料ダウンロードはこちら

【内容】
リンクアンドモチベーションの管理職研修は、独自の基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を基盤としています。管理職を「組織と個人のエンゲージメントを高める変革の起点」と位置づけ、部下の意欲を引き出し、自律的な成長を促すための具体的なスキルとスタンスを習得します。
【特徴】
研修を単発で終わらせず、組織診断サーベイ「モチベーションクラウド」と連動させることで、研修効果を可視化し、組織全体の課題解決に繋げる点が最大の特徴です。データに基づいて組織と個人の状態を客観的に把握し、科学的なアプローチでエンゲージメント向上を実現します。
【このような企業におすすめ】
- 従業員のエンゲージメントが低く、組織に一体感がない
管理職が部下の育成や動機づけに悩んでいる
企業のビジョンや戦略を現場に浸透させ、実行力を高めたい
▶︎資料ダウンロードはこちら
4. アルー株式会社

【内容】
アルーの管理職研修は、「成果を出すこと」と「部下を育成すること」の両立を実現する、実践的なプログラムです。特に、部下の主体性を引き出すための「育成力」向上に重点を置き、現場でのOJTを効果的に機能させるためのコミュニケーションやフィードバックスキルを徹底的に磨きます。
【特徴】
研修で学んだことを職場で実践し、その結果を持ち寄って議論する「アクションラーニング」を積極的に導入しているのが特徴です. 知識のインプットだけでなく、実践を通じた成功・失敗体験から学ぶことで、スキルの定着を確実にします。顧客企業の課題に合わせた柔軟なカスタマイズ力にも定評があります。
【このような企業におすすめ】
- 管理職がプレイングマネージャーとして多忙で、部下育成に手が回っていない
若手・中堅社員の自律的な成長を促し、次世代リーダーを育てたい
グローバルに活躍できるリーダーの育成も視野に入れている
▶︎資料ダウンロードはこちら

【内容】
日本能率協会(JMA)の管理職研修は、80年以上にわたり日本の産業界を支えてきた歴史と信頼に裏打ちされた、体系的なプログラムです。管理職に求められる役割やコンピテンシーを網羅的に定義し、リーダーシップ、問題解決、組織運営など、マネジメントの王道とも言えるスキルを基礎から応用まで着実に習得します。
【特徴】
全国主要都市で年間を通じて開催される「公開講座」のラインナップが非常に豊富な点が特徴です。1名からでも参加しやすく、他社の管理職との交流を通じて視野を広げることができます。ものづくりからサービス業まで、あらゆる業界の知見に基づいた普遍的で質の高いプログラムを提供しています。
【こんな企業におすすめ】
- 多様な部門があり、それぞれに必要なスキルが異なるため、研修を一括導入しにくい
初めて管理職になった人材に、マネジメントの基本を体系的に学ばせたい
自己流のマネジメントから脱却し、組織の標準となる考え方を浸透させたい
▶︎資料ダウンロードはこちら
【中小企業向け】おすすめの管理職研修 5選
中小・中堅企業においては、次世代の経営幹部育成と、組織変革への対応力強化を目的とした、実践的なプログラムが有効と考えられます。
事業の持続的成長のためには、経営者の右腕となる次世代リーダーの存在が不可欠です。
同時に、多くの中小・中堅企業は市場の変化や事業拡大に伴う「組織変革」の必要性に常に直面しています。
経営陣が掲げた変革のビジョンを現場で実行し、組織に浸透させるのは管理職の重要な役割です。そのため、次世代リーダーの育成と並行して、変化に対応できる組織基盤を築くための対応力強化が、研修の重要な目的となります。
個別のスキル習得に留まらず、PL理解や事業戦略の立案といった「経営視点」を養うプログラムが重視されます。また、必要なテーマだけを選んで受講できる公開講座など、柔軟かつ効率的に導入できるサービスも多く活用されています。
運営会社 |  株式会社インソース 株式会社インソース |  株式会社識学 株式会社識学 |  株式会社Schoo 株式会社Schoo |  株式会社PHP人材開発 株式会社PHP人材開発 |  株式会社FeelWorks 株式会社FeelWorks |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | ローワーマネジメント ミドルマネジメント | ミドルマネジメント トップマネジメント | ローワーマネジメント ミドルマネジメント | ミドルマネジメント トップマネジメント | ローワーマネジメント ミドルマネジメント |
| 導入企業例 | ・セーフィ株式会社 ・日本たばこ産業株式会社 ・オリックス生命保険株式会社 | ・株式会社ROXX ・株式会社林産業 ・株式会社オークファン | ・大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 ・大和ハウス工業株式会社 ・株式会社アトレ | ・パナソニックホームズ多摩株式会社 ・株式会社サンコウ・トータル・サービス ・タビオ株式会社 | ・本田技研工業株式会社 ・中部電力株式会社 ・株式会社市進ホールディングス |
| 料金体系 | 公開講座:3万円/人〜 | 個別見積もり | 月額制(1,650円/ID〜) | 公開講座:5万円/人〜 | 個別見積もり |

【内容】
インソースの管理職研修は、「明日から使える」実践的なスキル習得をコンセプトにしています。新任管理職向けの基本から、コンプライアンス、DX推進といった現代的な課題まで、2,500種類以上の豊富なプログラムを揃え、あらゆる現場の「困った」に即応できる解決策を提供します。
【特徴】
業界トップクラスの研修実績と、それに基づいた豊富なプログラムが最大の特徴です。講師派遣、公開講座、オンラインと多様な実施形態に対応しており、企業のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズも可能です。リーズナブルな価格設定で、費用対効果の高い人材育成を実現します。
【こんな企業におすすめ】
- とにかく実践的で、すぐに現場で使えるスキルを学ばせたい
管理職一人ひとりの課題が多様で、幅広いテーマから研修を選びたい
コストパフォーマンスを重視し、多くの管理職に研修機会を提供したい
▶︎資料ダウンロードはこちら
7. 株式会社識学

【内容】
識学の管理職研修は、「識学」という独自の組織運営理論のみに特化しています。組織内で発生する誤解や錯覚の原因を「意識構造」の観点から解き明かし、誰がやっても同じ成果を出せる、再現性の高いマネジメント手法を習得します。感情や感覚に頼らない、ロジカルで生産性の高い組織づくりを目指します。
【特徴】
唯一無二の「識学」理論が最大の特徴です。研修では、組織内のルール設定や権限委譲、評価の仕組みなどを徹底して学び、迷いのないリーダーシップを確立します。理論はシンプルかつ強力で、導入後すぐに現場での変化を実感しやすい即効性にも定評があります。
【こんな企業におすすめ】
- 役割分担が曖昧で、指示系統の混乱や生産性の低下が起きている
属人的なマネジメントから脱却し、組織全体の生産性を上げたい
部下の評価や育成の基準が曖昧で、不公平感が生じている
▶︎資料ダウンロードはこちら
8. 株式会社Schoo

【内容】
Schooの管理職研修は、8,000本以上の動画コンテンツを誇るオンライン学習プラットフォームを活用したものです。マネジメントの基礎理論から、DXやAIといった最先端のビジネストレンドまで、幅広いテーマを網羅。管理職が時間や場所を選ばずに、継続的に学び続けられる環境を提供します。
【特徴】
サブスクリプション型の法人向けプランにより、低コストで全社員が学び放題になるのが大きな特徴です。各業界の第一人者が登壇する生放送授業では、リアルタイムでの質疑応答も可能。自社の課題に合わせた研修パッケージの設計や、学習履歴の管理機能も充実しています。
【こんな企業におすすめ】
- 管理職が多忙で、まとまった研修時間を確保するのが難しい
最新のビジネス知識やITスキルを、常にアップデートさせたい
全社員に平等な学習機会を提供し、自律的な学習文化を醸成したい
▶︎資料ダウンロードはこちら
9. 株式会社PHP人材開発
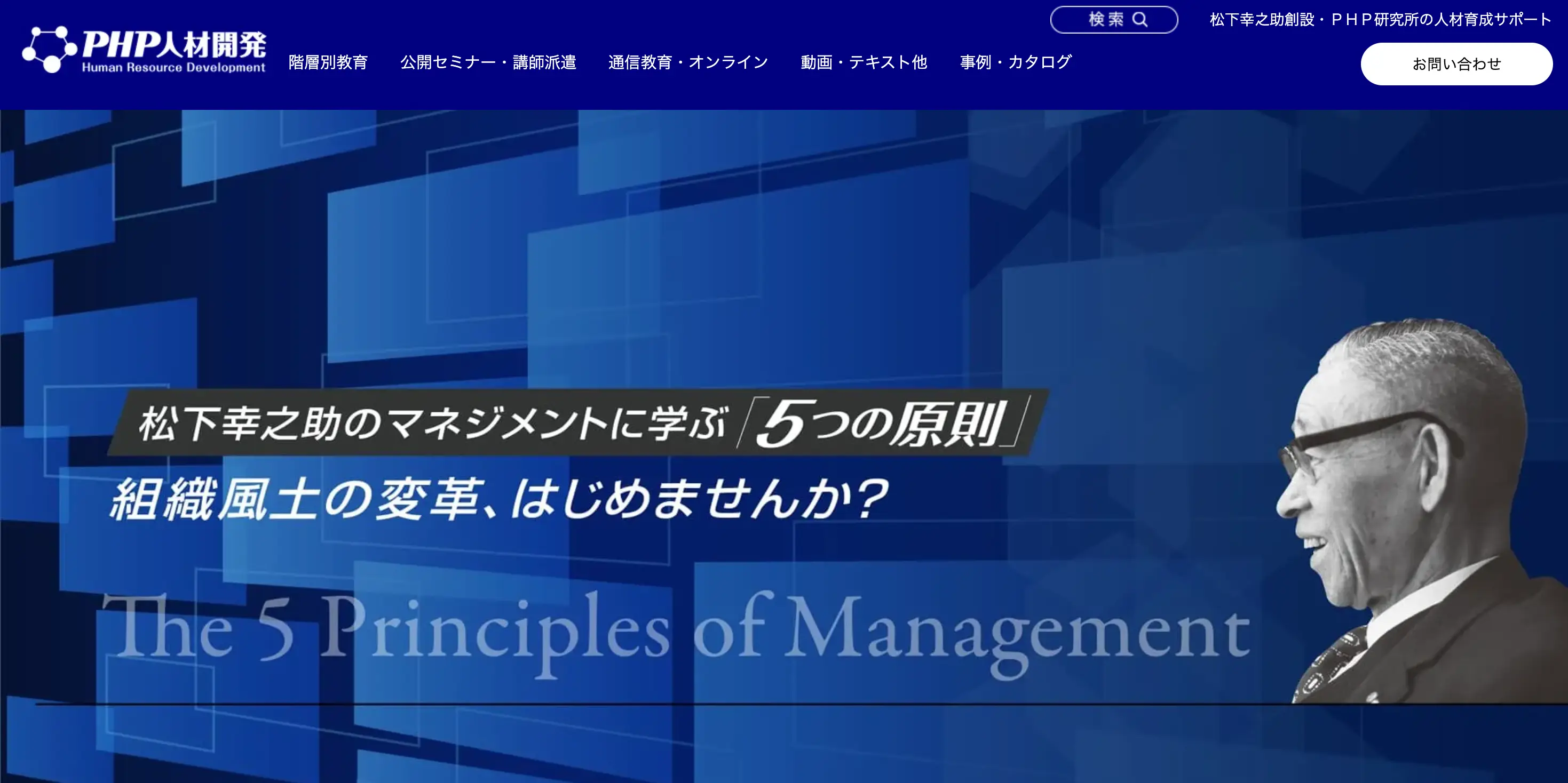
【内容】
PHP人材開発の管理職研修は、パナソニック創設者・松下幸之助の経営哲学を基盤としています。単なるスキルやテクニックの習得に留まらず、「素直な心」に代表されるような、リーダーとしての人間性や徳性を高めることに重きを置いたプログラムです。
【特徴】
時代を超えて通用する普遍的な人間学・リーダーシップ論を学べる点が最大の特徴です。研修は、講師の話を聴くだけでなく、内省と対話を重視したスタイルで進められ、受講者一人ひとりの人間的成長を促します。豊富な書籍との連動で、研修後も学びを深められる環境が整っています。
【こんな企業におすすめ】
- 企業の永続的な発展のために、幹部社員に確固たる理念や哲学を学ばせたい
小手先のスキルではなく、人間的な魅力で周囲を巻き込めるリーダーを育てたい
組織の一体感を醸成し、共通の価値観を持つリーダーシップチームを築きたい
▶︎資料ダウンロードはこちら
10. 株式会社FeelWorks

【内容】
FeelWorksの管理職研修は、「人が育つ現場をつくる」ことをミッションに掲げ、「上司力」の向上に特化しています。部下のキャリアを主体的に支援し、信頼関係を築くための具体的なコミュニケーション手法を学ぶことで、若手・中堅社員の離職を防ぎ、エンゲージメントの高い組織を実現します。
【特徴】
現場ですぐに実践できる、具体的なノウハウが豊富な点が特徴です。「ほめる」「叱る」「フィードバックする」といった日常的なコミュニケーションから、1on1ミーティングの進め方まで、部下の成長を支援する上司の「型」を習得できます。女性活躍推進に関する研修にも強みを持っています。
【こんな企業におすすめ】
- 若手社員の離職率が高く、人材の定着に課題を抱えている
管理職が部下の育成に苦手意識を持っており、関わり方が分からない
パワハラなどを防止し、心理的安全性の高い職場環境をつくりたい
▶︎資料ダウンロードはこちら
【ベンチャー成長企業向け】おすすめの管理職研修 5選
特に変化の激しいベンチャー・成長企業では、「組織の壁」を突破し、事業の成長を加速させることに特化した研修が求められる傾向にあります。
ベンチャー成長企業が直面するのは、「30名・50名・100名の壁」といった、事業の拡大に組織の成長が追いつかないという特有の課題です。理念の形骸化やマネージャーの疲弊といった問題は、一般的なマネジメント理論だけでは解決が難しい場合があります。
そのため、管理職には経営陣と現場をつなぐ「ハブ」としての役割が強く求められます。変化の速さに対応し、強い組織文化を構築するところまで踏み込むような、このフェーズの課題解決に深い知見を持つ研修パートナーを選ぶことが、成功の鍵となるでしょう。
| 運営会社 |  マネディク株式会社 マネディク株式会社 | 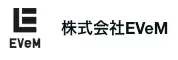 株式会社EVeM 株式会社EVeM |  アーティエンス株式会社 アーティエンス株式会社 |  株式会社NEWONE 株式会社NEWONE |  株式会社コーチ・エィ 株式会社コーチ・エィ |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | ローワーマネジメント ミドルマネジメント トップマネジメント | ローワーマネジメント ミドルマネジメント | ローワーマネジメント ミドルマネジメント | ローワーマネジメント ミドルマネジメント | ミドルマネジメント トップマネジメント |
| 導入企業例 | ・株式会社 PKSHA Technology ・株式会社ジーニー ・株式会社ネオマーケティング | ・スタディプラス株式会社 ・テラドローン株式会社 ・BASE株式会社 | ・株式会社ONE COMPATH ・株式会社CBホールディングス ・アクセルマーク株式会社 | ・株式会社ミクシィ ・カゴメ株式会社 ・山崎製パン株式会社 | ・保険会社 ・銀行 等 |
| 料金体系 | 都度見積もり 7ヶ月目以降は月額制(80,000円+ID数) | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり |

【内容】
マネディクの「運用型管理職研修」は、事業拡大期にあるベンチャー成長企業のマネジメント層を強化し、「目標に対し、実行が可能な組織」への変革を支援します。ベンチャー特有の課題に即したマネジメントの基礎を学べる動画コンテンツと、議論を通じて自社に合わせたアクションに落とし込む月次セッションを組み合わせ、組織の成長エンジンとなる管理職を着実に育成します。
【特徴】
最大の特徴は、研修を「やりっぱなし」にせず、企業が「内部で管理職を育て続ける」仕組みを構築する点にあります 。SaaSツール「スキルマップ」で学習内容の実践度を週次で可視化し、上長からのフィードバックを促すことで、強制的に育成サイクルを回します 。さらに、初期はマネディクが運営する研修を、最終的には社内の人材がファシリテーターとなって自走できる体制(インハウス化)への移行を支援します 。
【こんな企業におすすめ】
- 従業員数が「50名・100名・300名の壁」に直面し、部門間の壁やコミュニケーションの複雑化といった組織課題を抱えている
経営と現場の間に認識のズレがあり、戦略や方針が現場まで浸透しきれていない
管理職がプレイング業務に追われ、部下育成が後回しになり、「びっくり退職」など人材の流出が起きている
▶︎資料ダウンロードはこちら
12. 株式会社EVeM

【内容】
EVeMの管理職研修は、曖昧で属人化しがちなマネジメントを、誰でも実践できる「型」として提供することに特化しています。メンバーが自走する仕組みづくりや、効果的な会議の進め方など、具体的な業務シーンでそのまま使える、再現性の高いスキルとノウハウを習得します。
【特徴】
「マネジメントの型」という独自のコンセプトが最大の特徴です。研修で提供されるフレームワークやテンプレートは非常に実践的で、導入後すぐにチームの生産性向上や、管理職自身の負担軽減に繋がります。シンプルながらも本質的な内容で、成果に直結しやすいと評価されています。
【こんな企業におすすめ】
- 急成長によりマネジメントが属人化・我流になっている
プレイングマネージャーが多く、自身の業務で手一杯になっている
理論よりも、現場で今すぐ使える具体的なマネジメントの武器が欲しい
▶︎資料ダウンロードはこちら
13. アーティエンス株式会社

【内容】
アーティエンスの管理職研修は、組織開発の観点から設計されています。単に管理職個人のスキルを高めるだけでなく、研修を通じてチーム内の「関係性の質」を向上させ、心理的安全性の高い組織をつくることを目指します。対話と内省を促し、組織全体のパフォーマンスを根本から引き上げます。
【特徴】
体感型のワークショップや対話を重視した、深い気づきを促すプログラムが特徴です。講師が一方的に教えるのではなく、受講者自身が課題を発見し、解決策を考えるプロセスを大切にしています。個社の課題に合わせたオーダーメイドの設計で、組織変革までを視野に入れた支援を行います。
【こんな企業におすすめ】
- 組織の急拡大で心理的安全性が低下し、部門間の対立や指示待ちが増えている
メンバーが本音を言えず、新しいアイデアや挑戦が生まれにくい
研修をキッカケに、部署やチームの風土を根本から変えたい
▶︎資料ダウンロードはこちら
14. 株式会社NEWONE

【内容】
NEWONEの管理職研修は、新しい時代の価値観に合わせ、部下一人ひとりの「エンゲージメント」を高めることを主眼に置いています。若手社員の主体性を引き出し、自律的な成長を促すためのコミュニケーションや関わり方を学び、個の力を最大限に活かすマネジメントスタイルを確立します。
【特徴】
受講者同士の対話を重視した、インタラクティブな研修スタイルが特徴です。1on1ミーティングの質の向上や、キャリア支援の方法など、エンゲージメント向上に直結する実践的なプログラムが豊富に揃っています。研修を通じて、管理職自身の働きがいをも見つめ直すキッカケを提供します。
【こんな企業におすすめ】
- 中途採用の増加で社員のバックグラウンドが多様化し、組織の一体感が薄れている
若手社員のモチベーション管理や育成に課題を感じている
トップダウン型のマネジメントから、個の主体性を尊重するスタイルへ転換したい
▶︎資料ダウンロードはこちら
15. 株式会社コーチ・エィ

【内容】
コーチ・エィの管理職研修は、世界有数のコーチングファームとしての知見に基づき、「対話」による組織開発を主軸に置いています。管理職が部下の潜在能力を引き出す「コーチ型リーダー」となるためのスキルとマインドを習得。組織全体に対話の文化を根付かせ、持続的な成長を促します。
【特徴】
国際的な資格を持つプロのコーチが研修をファシリテートする、質の高さが最大の特徴です。単なるスキル研修に終わらず、エグゼクティブ・コーチングと組み合わせることで、経営層から現場まで一貫した組織変革を支援します。対話を通じて、組織が自ら課題を解決していく力を醸成します。
【こんな企業におすすめ】
- 優秀なプレイヤーを管理職に抜擢したが、個別の課題が複雑で画一的な研修では解決が難しい
指示命令型の組織風土から、自律創造型の組織風土へと転換したい
グローバルに通用するリーダーシップ開発や組織開発を目指している
▶︎資料ダウンロードはこちら
なぜ、ほとんどの管理職研修は「選んだ時点」で定着するかが決まっているのか?
結論、多くの管理職研修が定着せずに終わる根本原因は、研修を「選んだ時点」の基準そのものが間違っていることにあります。
ほとんどの企業が、自社の組織が抱える本質的な課題を深く診断することなく、「他社で流行っているから」「価格が手頃だから」といった表面的な理由で研修を選んでしまっているからです。これは、精密検査をせずに、ただ世間で評判の薬を処方するようなものです。症状に合っていなければ、効果が出ないのは当然と言えるでしょう。
事実、「管理職研修を導入したが、期待したほどの効果が得られなかった」という声は、企業規模を問わず、多くの現場で聞かれる共通の課題です。
ここで、ある企業の課題解決の歩みをご紹介します。
【導入事例】技術力に優れた企業が気づいた、「内製研修」の限界と新たな一手
システムエンジニアが9割を占める、株式会社ディマージシェア様。高い技術力を強みとする同社が直面していたのは、専門職から管理職への育成という、多くの企業が共感する課題でした。
同社は、社内でマネジメント教育に取り組むなど、早くからその重要性に気づき、行動していました。しかし、本業が多忙な中での研修の継続は難しく、また、マネジメントの「共通言語」がないため、学びが定着しにくいという現実に直面します。
この「良かれと思って始めた」内製研修の限界に気づいた同社は、個人の経験則に頼る育成から、仕組みで人を育てる外部プログラムへと舵を切りました。その結果、社内にマネジメントの共通言語が生まれ、約十年ぶりの組織改編を成功させるほどの大きな変革へと繋がったのです。
この事例が示すように、研修がうまくいかない状況は、研修の内容そのものが悪いというよりは、そもそも自社の課題と、それを解決するためのアプローチ(=研修の仕組み)がズレていることに起因する場合がほとんどです。
この「目的のズレ」を防ぎ、投資を確実な成果に結びつけるためには、どうすれば良いのでしょうか。
次の章では、そのための具体的な選定基準である「3つのポイント」について、詳しく解説していきます。
管理職研修選びで失敗しないための「3つのポイント」
失敗しない研修選びとは、単に研修会社のリストを比較することではありません。失敗をしないためには、自社の「目的(Why)」を明確にし、その目的達成に最適な「手段(What)」を見極め、そして成果を確実にするための「仕組み(How)」まで見通す、一連の戦略的なプロセスが必要です。
数々の急成長ベンチャーの組織課題を解決してきた専門家として、この3つのポイントについて、以下で詳しく解説します。
ポイント1: 自社の「課題」と「あるべき姿」から逆算する
管理職研修選びにおける最初の、そして最も重要なステップは、研修の目的を、自社の「現在の課題」と「未来のあるべき姿」とのギャップを埋めるものとして具体的に設定することです。
もし、あなたが体調不良で病院に行ったとして、医師が問診も診察もせずに「世の中で評判の良い薬です」と言って薬を処方したら、どう思うでしょうか?おそらく、その医師を信用できないはずです。
研修選びも全く同じです。目的が曖昧なままでは、研修は単なる気休めの「お勉強会」で終わってしまいます。「100名の壁」で起きる部門間の対立を解消したいのか、理念を体現する次世代リーダーを育てたいのか。組織の課題という「診断」が具体的であるほど、研修という「処方箋」の効果は明確になります。
この目的を明確にするアプローチには、大きく分けて2つの起点が存在します。
- 「現在起点」で考えるアプローチ
- 今まさに起きている「離職率の悪化」や「部門間での対立」といった、目下の解決すべき組織課題を言語化
- 「未来起点」で考えるアプローチ
- 「3年後に事業を倍にするために、どのような価値観や行動様式が浸透した組織(=カルチャー)であるべきか?」といった、その理想像から逆算する方法
どちらの起点から考える場合でも、最終的には「現在地」の課題認識と「未来」の理想像の両方を結びつけ、そのギャップを埋めるための具体的な目標を設定することが重要です。
例えば、「マネジメントスキルを向上させる」という漠然とした「未来起点」のゴール設定では、研修担当者と現場の管理職との間で認識のズレが生じがちです。
一方で、「100名の壁を突破するため、部門間の連携を促進できる次世代リーダーを3名育成する」というように目的が具体的であれば、選ぶべき研修も、測るべき成果も自ずと明確になります。
ポイント2:目的達成に繋がるプログラムかを見極める
目的が明確になったら、次にその目的を達成できる研修プログラムかどうかを吟味します。
ここで重要なのは、設定した目的と、研修という手段が一直線に繋がっているかを見極めることです。
どんなに素晴らしい目的を掲げても、それを達成する手段がズレていては意味がありません。
特に管理職は、日々の業務に追われる中で研修時間を作っています。「興味深い学びはあったが、現場では使えない」といった抽象的な学びで終わらせるわけにはいきません。
では、具体的にどう見極めれば良いのでしょうか。ここでは、実際に世の中に存在する研修プログラムを例に、「良い研修」と「注意すべき研修」の違いを見てみましょう。
【注意すべき「汎用性」「専門性」が欠けた研修】
① 著名経営者やスタープレイヤーによる単発の研修(=汎用性がない)
② オンラインの「受けっぱなし」eラーニング研修(=専門性がない)
【理想的な研修プログラムの例】
①理論と実践を組み合わせた「ブレンデッド型の研修」
これが、現在最も効果的と言われる研修形態の一つです。
まず、マネジメントの基本理論(汎用性)を、eラーニングなどで事前にインプットします。
そして、研修当日は講義を聞くのではなく、事前学習した理論を元に、「自社のリアルな課題」を持ち寄って、参加者同士で徹底的に議論・演習します(専門性)。「この理論を、うちの部署で実践するにはどうすれば良いか?」という問いに、講師はファシリテーターとして関わり、具体的な解決策へと導くことがブレンデッド型研修の強みです。
マネジメントの普遍的な原理原則(汎用性)を学び、それを「自社の場合だったら、どう活かすべきか?」と、自分たちの課題に合わせて議論し、実践する機会(専門性)が設計されているか。
この視点を持つことで、研修選びで失敗するリスクは必然的に下がっていきます。
ポイント3:「行動変容」を促し、測定する仕組みがあるか
研修の成果である「行動変容」を促し、客観的に測定できる2つの仕組みがプログラムに組み込まれているかを確認しましょう。
大前提として、研修は「投資」であり、その最大のリターン(ROI)は参加者の「行動変容」に他なりません。この変化を測定できなければ、研修が本当に効果があったのかを誰も判断できず、結局は「やりっぱなし」のコストで終わってしまいます。
以下では、人の「行動変容」を促し、継続させるためには、どのような仕組みが有効なのかをご説明します。
【①行動の「解像度」を上げる】
多くの人にとって、行動の心理的なハードルは、その行動が具体的であるほど低くなります。
特に、新しい行動を促す上では、「何をすべきか」の解像度を上げてあげることで、最初の一歩を踏み出しやすくなります。
研修においては、「学習→実践→評価・改善」という学習サイクルがこの役割を果たします。
スポーツを例に取ると分かりやすいでしょう。以下のサイクルを繰り返して、初めてスキルは定着します。
(学習)一度トレーニング方法を教わっただけでは不十分
↓
(実践)実際に自分でやってみて
↓
(評価)トレーナーからフィードバックをもらい
↓
(改善)やり方を修正する
このサイクルを回す中で、抽象的な理論が具体的な実践へと翻訳され、「今、自分が何をすべきか」が明確になっていきます。
【②成長の「効果」を可視化させる】
また、新しい行動を継続させる上で極めて有効なのが、「自分は成長している」という実感です。
ビジネスの現場では、その評価が「最近、A課長はよくやっている」といった感覚的なものになりがちです。そこで重要になるのが、「効果を可視化」し、客観的な事実に基づいて成長を実感させるというアプローチです。これは研修を導入する上で、合理的な戦略の一つになります。
ここまで解説したように、研修選びで最も重要なのは、学習を「やりっぱなし」にせず、参加者の「行動変容」を促し、測定する『仕組み』が組み込まれているかを見極めることです。
私たちマネディクが、月に一度の「グループセッション」と日々の実践を可視化する「SaaSツール」を組み合わせたサービスをご提供しているのも、まさにこの思想に基づいています。
しかし、どんなに優れた仕組みを持つ研修を選んだとしても、それだけで成果が保証されるわけではありません。その効果を120%引き出すためには、研修を導入する「企業側の工夫」が不可欠です。

次の章では、研修効果を最大化するために企業が踏むべき「3つのステップ」について、詳しく見ていきましょう。
研修効果を最大化する管理職研修の「3つのステップ」
研修の投資対効果を最大化するためには、「目的の定義」「実践の設計」「行動変容の測定」という3つのステップを踏むことが不可欠です。
これらのステップは、研修を単発のイベントで終わらせず、持続的な成果に繋げるための普遍的な成功法則と言えます。
ステップ1:参加者が「自分事」として考えられるようにする
研修の成功は、ゴールを明確に言語化し、参加者一人ひとりが「自分の課題解決に役立つ」と当事者意識を持って取り組めるかという観点が重要になります。
なぜなら、会社としての目的を一方的に伝えるだけでは、参加者は「やらされ仕事」と感じてしまい、研修への主体的な参加が期待できないためです。成功の9割は、この事前準備で決まるといっても過言ではありません。
ステップ2:研修と現場を往復させ、「実践」の機会を設計する
本当の行動変容を加速させるには、知識のインプット(研修)とアウトプット(現場での実践)をセットで設計し、理論と実践を往復する学習サイクルを意図的に作ることが不可欠です。
一度インプットしただけの知識は、抽象的なままだと現場の多忙さの中ですぐに忘れ去られてしまいます。
そのため、インプットした知識を現場ですぐに実践し、改善できるように小さなステップを設計していく必要があります。
具体的な方法としては、研修後に参加者同士で実践報告会を行ったり、上長との1on1で「学んだ内容を、この業務でこう活かした」といった対話の機会を設けたりすることが挙げられます。また、研修内容に基づいた実践的なアクションプランを各自が作成し、その進捗を定期的に共有する仕組みも有効です。
ステップ3:「行動変容」を測定・評価し、次の改善へ繋げる
研修の成果は「満足度」ではなく「行動が変わったか」で測り、その結果を客観的なデータとして可視化し、次の改善アクションに繋げる仕組みを構築することが必要です。
行動変容を客観的に評価することで、初めて研修の投資対効果(ROI)を正しく把握できます。また、データに基づき、個人の成長と組織全体の継続的な改善を促します。
研修後の「満足度アンケート」は、あくまで研修が有益な”体験”であったかを示す指標に過ぎず、参加者の”能力”が向上したか、”行動”が変わったかを示すものではないからです。
高い満足度が、必ずしも業績向上に繋がるとは限りません。真の投資対効果(ROI)は、研修をきっかけに参加者の行動がどう変わり、それがチームや組織の成果にどう結びついたかを把握して初めて、正しく測定できたと言えます。
具体的な仕組みとしては、研修前後の360度評価で行動の変化を比較したり、評価項目の1つに研修で学んだスキルの実践度を入れたりする方法が考えられます。また、研修で目指した行動変容が、実際の業績や離職率といった事業KPIにどのような影響を与えたかを定期的に振り返る場を設けることも重要です。
マネジメント研修に関するよくある質問(FAQ)
Q. 管理職研修はオンラインでも受けられるのですか?
A. もちろん可能です。
現在では多くの管理職研修がオンラインで提供されており、場所を選ばずに学べるという大きなメリットがあります。
ただし、一言で「オンライン研修」と言っても、その形式と効果は大きく異なります。主に以下の2種類に大別できます。
- 動画視聴型のeラーニング:
- 知識や理論をインプットするのに適しています。手軽な反面、「受けっぱなし」になり、実践に繋がりにくいという側面もあります。
- 双方向のライブセッション:
- 講師や他の参加者とリアルタイムでディスカッションや演習を行います。学んだ知識を「自社の場合」にどう適用するかを議論することで、学びが深まります。
最も効果的なのは、この2つを組み合わせた「ブレンデッド型の研修」です。事前にeラーニングで知識をインプットし、当日はオンラインのライブセッションで実践的な議論に集中する。重要なのはオンラインかオフラインかという形式ではなく、学んだ知識を「行動変容」に繋げるための仕組みが設計されているかどうかです。
Q. 管理職研修の費用相場は、どのくらいですか?
A. 研修の形式や期間によって大きく異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
オンライン動画型: 月額数千円〜数万円/ID
公開講座(1日): 3万円〜10万円/回
講師派遣型(1日): 30万円〜100万円/回
ただし、重要なのは価格そのものではなく、その投資に見合う「行動変容」というリターンが得られるかです。
本記事で解説した「選び方の3つのポイント」、特に「行動変容を促し、測定する仕組みがあるか」という観点から、費用対効果を判断することが不可欠です。
Q.「研修は意味がない」という声も聞きますが、本当に効果はあるのでしょうか?
A. 「やりっぱなし」の研修であれば、その声は正しいでしょう。
多くの研修が意味をなさないのは、選び方の基準が間違っているからです。
研修の効果は、
(ポイント1):自社の課題と目的を明確にし
(ポイント2):目的達成に繋がる実践的なプログラムを選び
(ポイント3):研修後の行動変容までを設計・測定する
という3つのポイントを押さえて初めて、有効なものになります。
正しく選び、正しく運用すれば、管理職研修は組織を動かす強力なエンジンとなります。
Q. 研修に参加させるべきなのは、どのような管理職ですか?
A. 組織への影響度で戦略的に選抜すべきです。
具体的には、
①経営と現場をつなぎ、カルチャー浸透の「ハブ」となる管理職
②「組織の壁」に直面し、最も大きな成長痛に悩んでいる管理職
を優先します。
重要なのは、個人(点)のスキルアップではなく、管理職層(面)で捉え、組織が自走するための共通言語をインストールすることです。
まとめ:管理職研修は、企業の「未来のカルチャー」を創る戦略投資である
本記事では、数ある選択肢の中から、本当におすすめできる管理職研修を厳選し、その選び方の3つのポイントから成功の秘訣までを専門家の視点で徹底解説してきました。
その中でも最も重要なのは、管理職の研修選びが単なるスキル習得の場でなく、「未来のカルチャーを選ぶ」行為に他ならないという視点です。
なぜなら、
- 事業の持続的な成長を支えるのは、そこで働く「人」であり、その人々の才能を最大限に引き出す土壌こそが「カルチャー」だからです。優れたカルチャーがなければ、どれだけ優秀な人材を採用し、育成や評価といった人事施策に投資しても、その効果は限定的となり、才能が開花する前に離職してしまいます。
そして、そのカルチャーを日々創り出し、現場に浸透させていく役割を担うのが「管理職」に他なりません。管理職の言動一つひとつがチームの文化を形成し、経営の意思を現場の行動へと翻訳します。だからこそ、管理職研修は、企業の未来を創る「カルチャーへの戦略的投資」と言えるのです。
経済学者のピーター・ドラッカーも「カルチャー浸透」の重要性は説いています。
「どれだけ優れた戦略があっても、それを実行する企業のカルチャーに問題があれば戦略は機能しません。逆に、そこまで優れた戦略がなかったとしても、カルチャーが優れており、実行が卓越していればゴールを達成できることもあります。」
上記にある通り、ベンチャー成長企業が急成長を続けるためには、いかに「カルチャー浸透」をさせるかにかかっています。
マネディクはベンチャー企業を”爆速成長”させるためのサービスをご提供しており、累計300社の成長企業をご支援してきました。
まずは以下の資料からサービスの情報をご確認ください!



