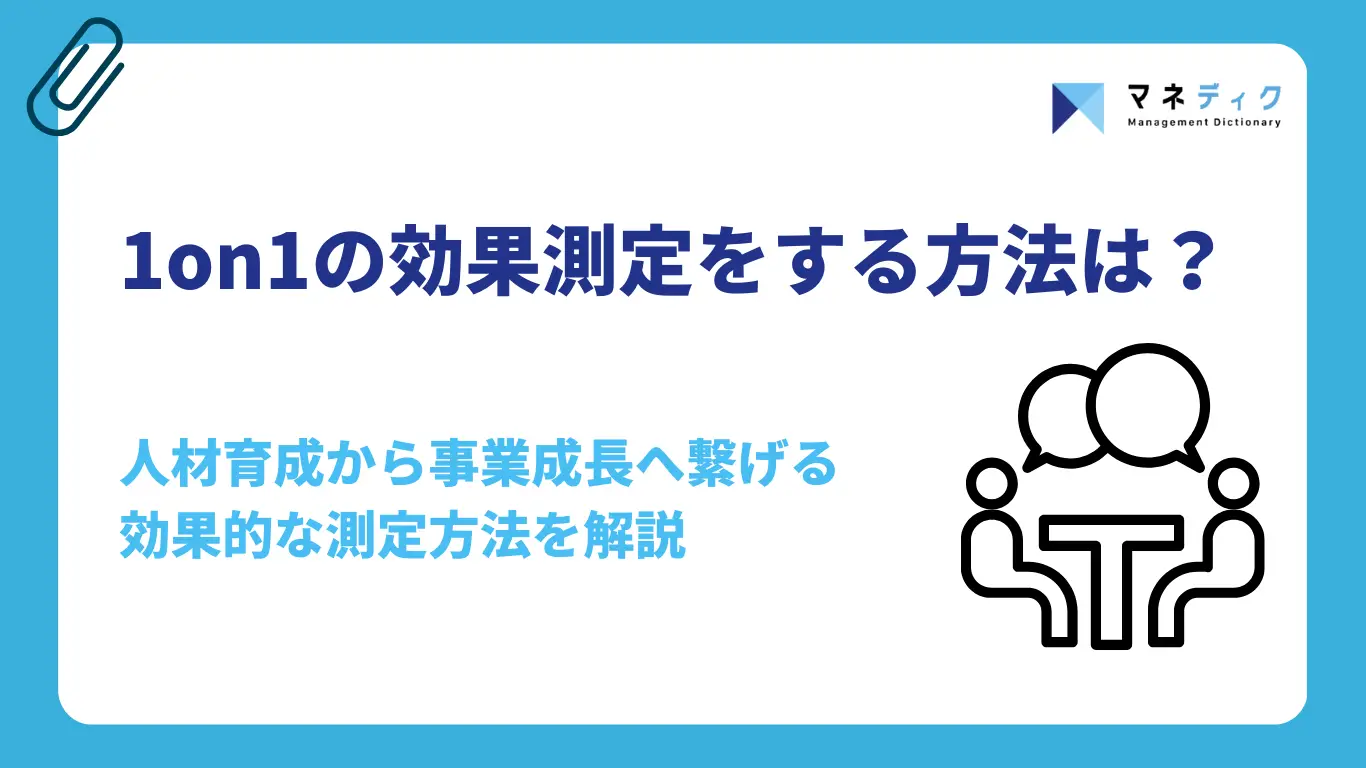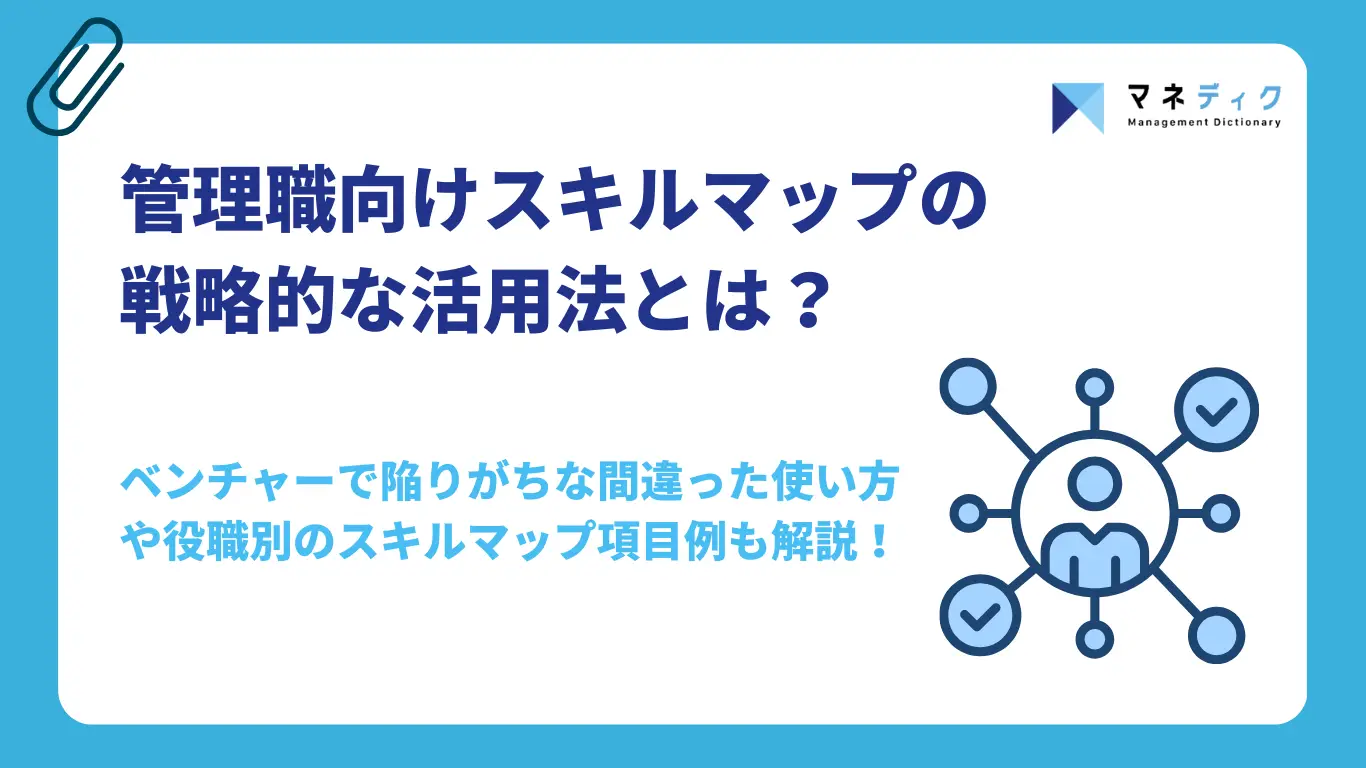スキルマップは意味ない?形骸化する5つの原因と効果的な運用方法を解説
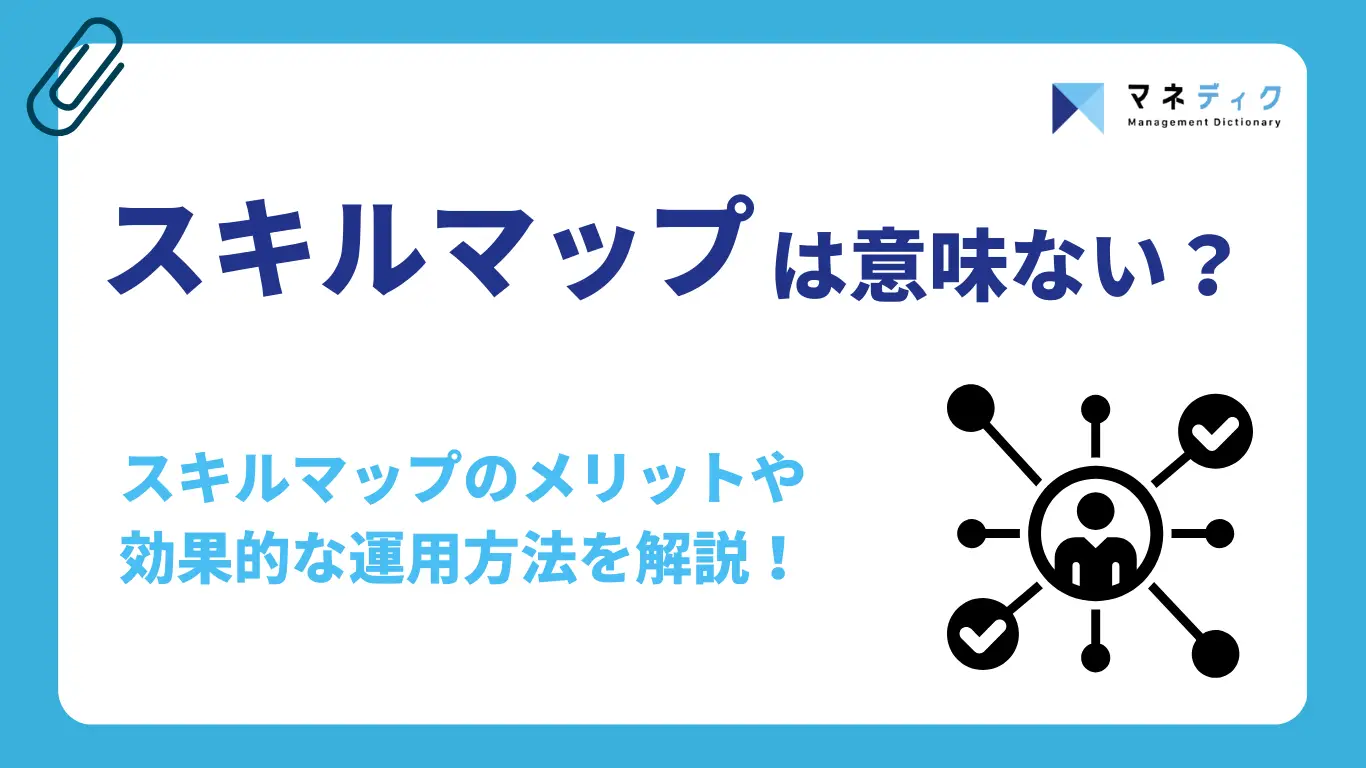
スキルマップはなぜ「意味ない」と言われ、形骸化するのか?
多くの企業でスキルマップが形骸化してしまうのには、共通した原因があります。
実際のよくある原因を5つご紹介するので、自社の状況と照らし合わせながら、どこに問題があるのかを確認してみましょう。
原因1:作成・導入が目的化している
最も多い失敗パターンが、スキルマップを「作ること」自体がゴールになってしまうケースです。
経営層からの指示で導入が決まったものの、「何のためにスキルを可視化するのか」「可視化して得られたデータを、どう人材育成や配置に活かすのか」という本来の目的が、現場の管理職や社員に全く浸透していないのです。
目的が曖昧なままでは、社員は「また新しい仕事が増えた」とやらされ感を感じるだけです。
原因2:更新・運用に手間がかかりすぎる
スキルマップが「意味ない」と思われ、形骸化してしまう原因の2つ目は、スキルマップ自体の更新や運用に手間がかかりすぎることです。
特に、マネージャーとプレイヤーの両側面を持つプレイングマネージャーが一般的なベンチャー/成長企業では、管理職自身の業務も多忙を極めます。
その中で、部下全員のスキルを一つひとつ評価して、フィードバックを行う時間は大きな負担となります。
Excelなどで手作業で管理している場合、更新作業の煩雑さから、次第に運用が疎かになりがちです。「半年に一度」「一年に一度」の更新時期に、過去の記憶を頼りに慌てて評価を埋める、といったことが常態化してしまいます。
原因3:評価制度と連動していない
スキルマップが「意味ない」と思われてしまう原因の3つ目は、スキルマップと評価制度が連動していないことです。
社員にとって、自身の評価は給与や昇進に直結する重要な関心事です。
もしスキルマップの評価が、実際の人事評価やキャリアアップの道筋と全く連動していなければ、「これを頑張っても意味がない」と感じてしまうのは当然です。
スキルマップ上では高いスキルレベルに到達しているのに、それが評価や処遇に全く反映されない状態では、真剣に取り組むモチベーションは生まれません。
原因4:スキル項目が抽象的・実務と乖離している
スキルマップが形骸化してしまう原因の4つ目は、スキルマップの項目が抽象的、また実態と乖離していることです。
「リーダーシップ」「課題解決能力」といった抽象的なスキル項目を設定してしまうと、評価者によって解釈が大きく異なり、客観的な評価が困難になります。
また、現場の実務内容とスキル項目がかけ離れている場合、社員は「今の仕事と関係ないのに、なぜ評価されなければいけないのか」と不満を抱きます。汎用的なスキル項目を並べてしまって、結果機能しないということは往々にして起こり得ます。
そのため、スキルマップを作成、または導入する際は抽象的な項目や汎用的な項目にするのではなく、各マネージャーが正しく評価できるレベルの具体的なものや自社の状況に即したカスタマイズされたもので運用するよう心がけましょう。
原因5:管理職(運用者)が活用方法を理解していない
スキルマップが意味ないと言われてしまう原因の5つ目は、スキルマップの運用者である管理職・マネージャーの方自身が適切な活用方法や目的を理解していないことです。
スキルマップは、作成して終わりではありません。1on1面談でフィードバックしたり、次の成長目標を共に設定したりと、部下とのコミュニケーションツールとして活用してこそ価値が生まれます。
しかし、管理職自身がその具体的な活用方法を理解していなければ、単なる評価シートの提出を求めるだけで終わってしまいます。制度を作る・導入する側である人事担当者や経営者と、実際に運用する側である管理職との間で、目的と活用方法の目線が合っていないのです。
「意味ない」スキルマップが組織にもたらす3つの弊害と予防策
「意味がない」と言われて形骸化したスキルマップをそのまま惰性で運用することは、単に「効果がない」だけでは済まず、組織全体に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
以下のような状況に陥らないように、スキルマップを運用するうえでの予防策も一緒に解説していきますので、スキルマップ導入を考えている担当者・経営者の方、もしくは思うようにスキルマップが組織で機能していないことに課題を感じられている方は必ずご一読ください。
弊害1:社員のモチベーションとエンゲージメントの低下
納得感のない評価や、実態と乖離したスキル項目は、社員の不満を増大させます。自身の頑張りが正当に評価されていないと感じることで、仕事へのモチベーションは低下します。
「このスキルマップ通りの項目を実践してもどうせ正しく評価されない」という諦めは、組織全体へのエンゲージメント低下を招き、生産性の悪化に繋がります。
これらの予防策としては、「ある程度評価制度と連動させたスキル項目にしておくこと」「スキルマップを実際に運用するマネージャーとメンバーにスキルマップの導入背景や目的を明確に伝えておくこと」が挙げられます。
弊害2:育成の場当たり化と人材流出
スキルマップがまったく機能しないことで、人材育成は場当たり的・属人的になります。
社員は「この会社でどう成長していけば良いのか」「どのようにスキルアップしていけば良いのか」というキャリアパスを描けず、成長実感を得られません。
特に、成長意欲の高い優秀な人材ほど、自身のキャリアに不安を感じ、より明確な成長機会を求めて組織を去ってしまうリスクが高まります。
人材育成・マネジメントの属人化は確実に組織を壊します。
こちらの予防策としては、「スキルマップを運用するマネージャーとスキルマップの運用背景・目的を徹底的に合意しておくこと」「スキル項目を少しストレッチな項目に更新し続けること」が挙げられます。
弊害3:マネジメントコストの増大
一見すると何の変哲もない作業に見えるかもしれませんが、形骸化した制度の運用には、目に見えないコストがかかり続けています。
管理職やマネージャーの方が評価シートの提出を催促する時間、社員が仕方なくシートを埋める時間。
これらの積み重ねは、組織全体で見れば膨大なマネジメントコストです。本来もっと生産的な業務に使えるはずの時間が、意味のない作業に費やされているのです。
前提、効果的なスキルマップの運用ができれば良いのですが、とはいえ適切に運用しても運用コストは高めな施策なので、できればExcelやスプレッドシートなどではなくSaaSで管理できるサービスの導入がおすすめです。
SaaSのツール上で簡単に操作できるので、運用コストも軽減できますし、スキルの不足の可視化も容易なのでメンバー自身もゲーム感覚で利用することができます。スキルマップにかける運用コストを減らしたい、とはいえ効果が実感できる施策にしたいと考えている経営者・担当者の方はSaaSのスキルマップの導入をご検討ください。
特に我々マネディクは、これまで300社以上のベンチャー/急成長企業にマネジメント研修を導入していただいた実績・経験をもとに各社に完全カスタマイズしたSaaSスキルマップのご提供をさせていただいております。
抽象的・汎用的なものではなく、ベンチャー/急成長企業特有の環境下を生き抜くためのより実践的なスキルマップを活用したい経営者・担当者の方はまず以下から無料でサービス資料のダウンロードができますので、お気軽にご覧ください。

スキルマップがもたらす4つのメリット
一方で、スキルマップを正しく設計し、運用することができれば、組織にとって計り知れないメリットをもたらします。形骸化のリスクを乗り越えた先にある、本来の価値を再確認しましょう。
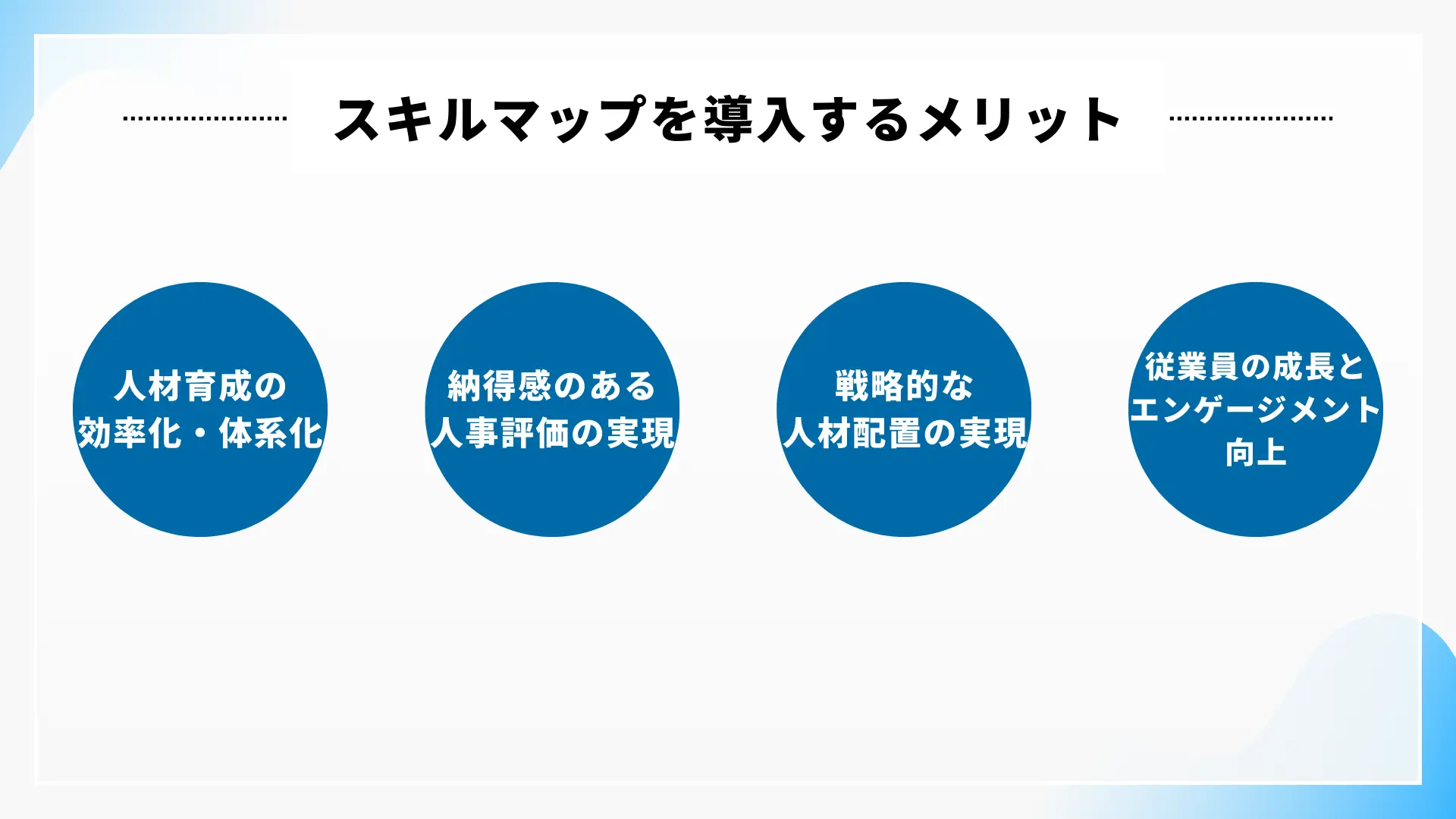
メリット1:人材育成の効率化と体系化
社員一人ひとりの「できること(保有スキル)」と「できないこと(習得すべきスキル)」が明確になるため、場当たり的な研修ではなく、個々の課題に合わせた計画的な育成が可能になります。
例えば、特定のスキルが部署全体で不足していることが分かれば、集合研修を企画するなど、データに基づいた育成戦略を立てられます。
また、スキルが言語化・体系化されることで、上司と部下の間で「目指すべき姿」についての共通認識が生まれます。これにより、OJTやフィードバックの質が向上し、組織全体で育成方針が統一され、育成の質が安定します。
メリット2:公正で納得感のある人事評価の実現
客観的な基準に基づいて評価が行われるため、評価者の主観や感覚によるブレがなくなり、社員の納得感が高まります。
「なぜこの評価なのか」が具体的な行動レベルで明確になることで、評価者である管理職と部下との信頼関係も深まります。
特に、評価面談が建設的な対話の場に変わる効果は絶大です。単なる結果の通達ではなく、「このスキルが伸びたから、次のステップとしてこの業務に挑戦しよう」といった、未来に向けた前向きなコミュニケーションが可能になるのです。
メリット3:戦略的な人材配置(適材適所)の実現
「誰が」「どのようなスキルを」「どのレベルで」持っているのかが組織全体で可視化されるため、新規プロジェクトの立ち上げや欠員補充の際に、最適な人材を迅速にアサインできます。
これにより、個人の強みを最大限に活かし、チームとしてのパフォーマンスを高める「適材適所」が実現します。
さらに、将来の事業戦略を見据え、「今後どのスキルを持つ人材が不足するのか」を予測し、計画的な採用や育成(サクセッションプラン)につなげることも可能です。
メリット4:従業員の主体的な成長とエンゲージメントの向上
自身の現在地と目指すべきゴール、そしてそのために必要なスキルが明確になることで、社員は主体的にキャリアを考え、自律的に学習するようになります。
「何を頑張れば評価され、成長できるのか」というキャリアパスが見えることは、日々の業務に対するモチベーションを高めます。
成長への道筋が見えることは、仕事へのエンゲージメントを高め、組織全体の活力を生み出します。結果として、社員一人ひとりの成長が、組織の成長へと直結する好循環が生まれます。
スキルマップに関するよくある質問
Q. スキルマップにデメリットはありますか?
A. はい、あります。
作成や更新に時間がかかる点、評価基準が曖昧だと社員の不満に繋がる可能性がある点、スキル項目を意識しすぎるあまり本来の業務目的を見失う可能性がある点などが挙げられます。
これらのデメリットは、目的を明確にし、運用を仕組み化することで最小限に抑えることが可能です。
Q. テンプレートを使ってもいいですか?
A. はい、テンプレートの活用は効率的です。
厚生労働省などが提供するテンプレートは、項目を洗い出す際の参考になります。
ただし、テンプレートをそのまま使うのではなく、必ず自社の実態に合わせて「あるべき人材像」から逆算し、項目をカスタマイズすることが、形骸化させないための重要なポイントです。
Q. スキルマップの導入に失敗しないためには?
A. 失敗を避けるためには、「導入目的の明確化と共有」「現場の管理職や社員を巻き込んだ項目設計」「評価制度との連動」「継続可能な運用フローの構築」の4点が不可欠です。
特に、最初から完璧を目指さず、スモールスタートで試験導入し、現場のフィードバックを得ながら改善していく進め方が成功の鍵となります。
Q. 導入が効果的な業界はありますか?
A. 必要なスキルや習熟度が比較的明確に定義しやすい、IT業界(エンジニアなど)、製造業、建設業などは特にスキルマップとの親和性が高いと言われています。
しかし、職種ごとの専門スキルを定義すれば、どのような業界でも効果的に活用することが可能です。
Q. 評価の段階(レベル)はどのように設定すればいいですか?
A. 一般的には3〜5段階で設定するケースが多いです。
「レベル1:指示があればできる」「レベル2:一人でできる」「レベル3:他者に指導できる」のように、各段階を具体的な行動で定義することが重要です。
段階を細かくしすぎると評価が煩雑になるため、自社の運用に合った粒度で設定しましょう。