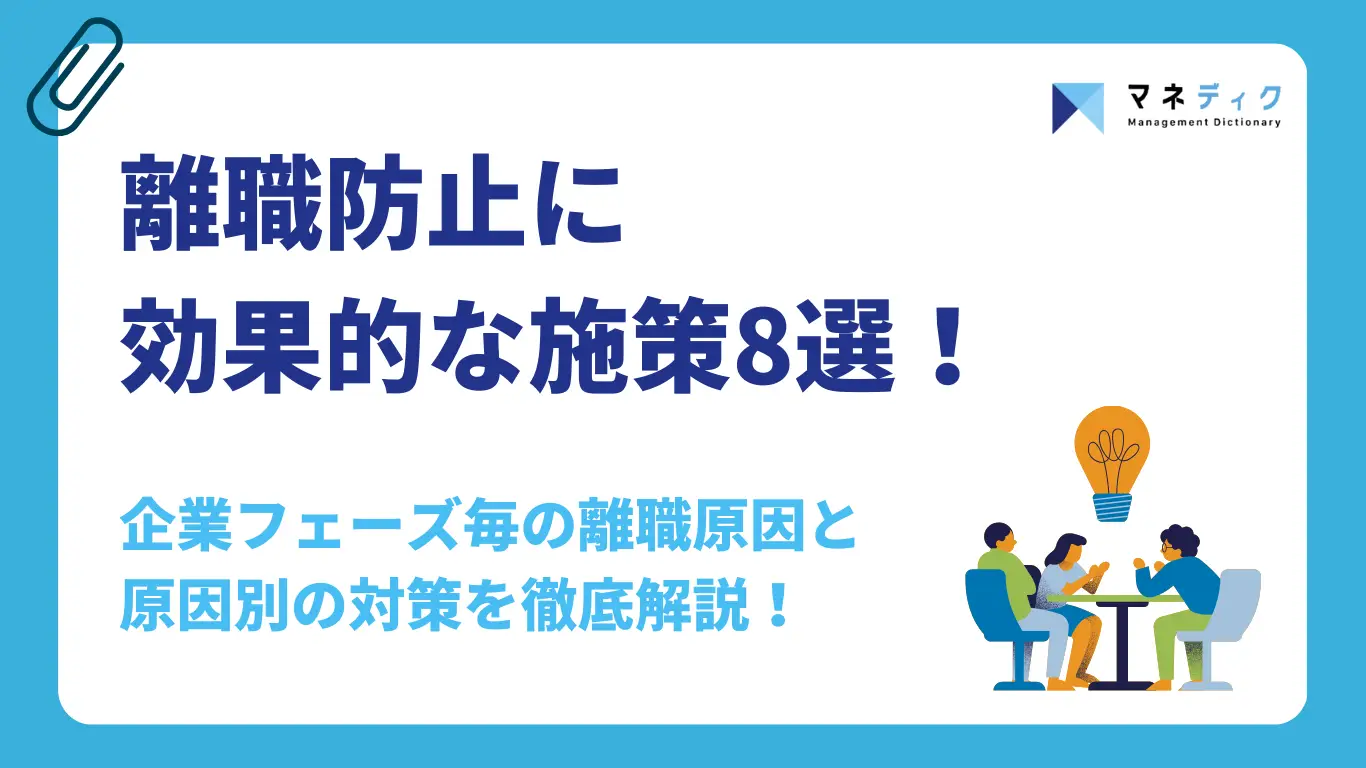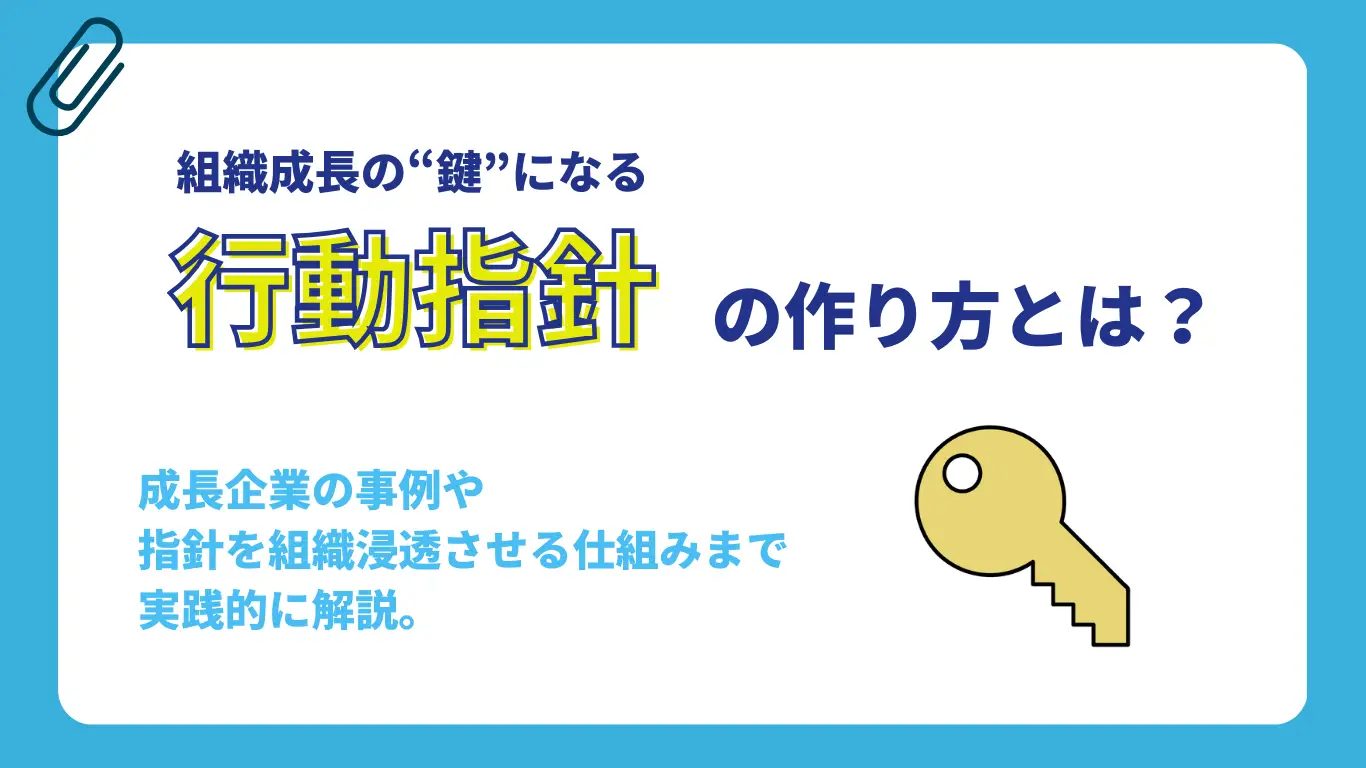30人・50人・100人の壁とは?原因と対処法を役職別の視点で徹底解説
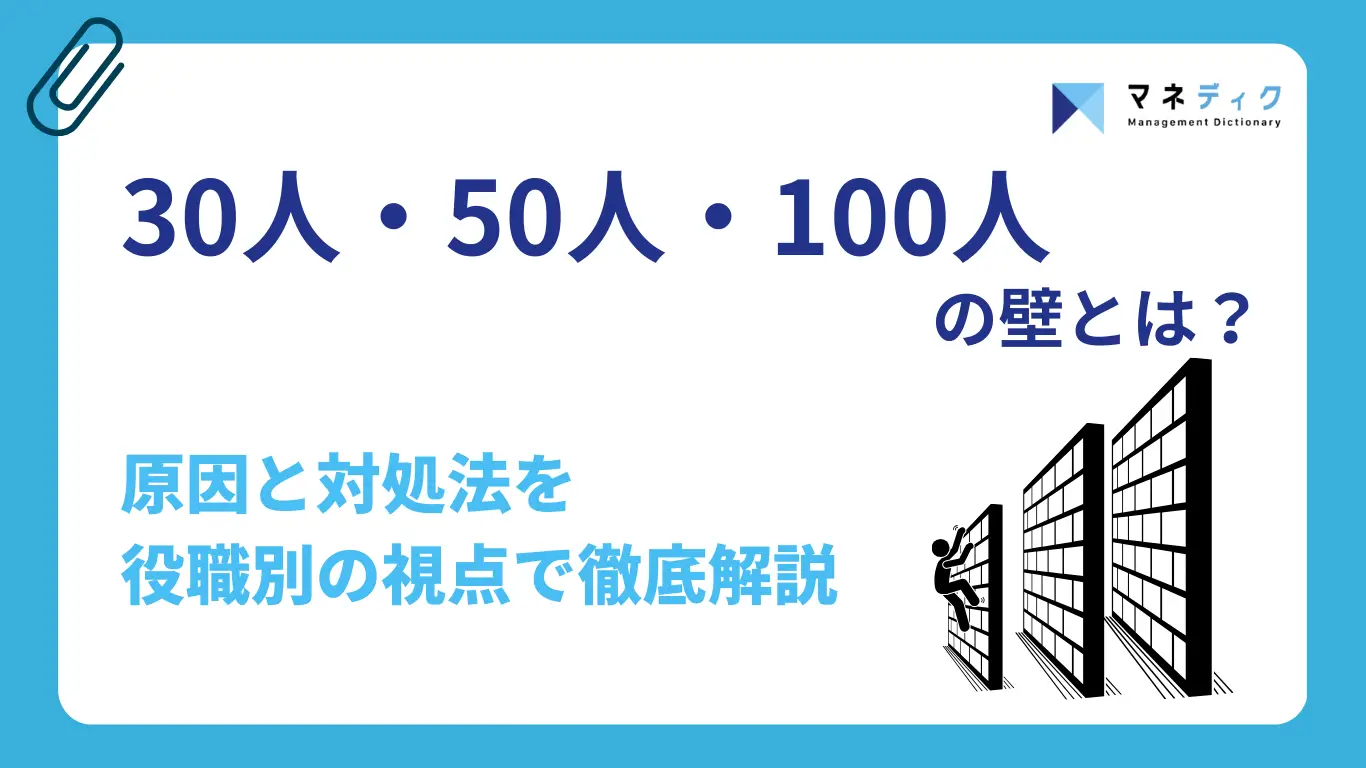
「30人の壁」「50人の壁」「100人の壁」とは?
なぜ「人数」で壁が発生するのか
そもそも、なぜ「30人」「50人」「100人」といった特定の従業員数で、組織は壁にぶつかるのか。それは、組織の規模拡大に伴い、コミュニケーションの「質」と「量」が劇的に変化するからです。
創業期の数名の段階では、経営者の想いは「阿吽の呼吸」でメンバーに伝わります。しかし、人数が増えるにつれて、物理的な距離や関係性の希薄化が生まれ、直接的なコミュニケーションだけでは意思の疎通が困難になります。
特に、創業期からいるメンバーと、組織が拡大してから加わったメンバーとの間には、価値観や仕事へのスタンスに微妙なズレが生まれやすくなります。
この「意識の差」が、連携ミスやモチベーションの低下といった問題を引き起こす根本原因になります。つまり「組織の壁」とは、企業の成長につきものであり、コミュニケーションの仕組みをアップデートせよというサインなのです。
各組織フェーズで起こる問題の全体像
企業の成長フェーズごとに発生する組織の壁は、その課題も乗り越え方も異なります。
まずは、自社がどのステージにいるのか、そして次にどのような課題が待ち受けているのか、全体像を把握しましょう。
| フェーズ | 典型的な事象 |
| 30人の壁 | ・経営者の意図が正確に伝わらない ・創業メンバーと中途入社組の間に溝ができる ・理念やビジョンが形骸化し始める |
| 50人の壁 | ・社長が全業務を把握できなくなる ・部門間の連携がうまくいかず、セクショナリズムが蔓延する ・ミドルマネージャーが育たず、現場が疲弊する |
| 100人の壁 | ・誰が何をしているか分からなくなり、組織の一体感が失われる ・評価や報酬に対する不満が噴出する ・情報が断片化し、意思決定スピードが鈍化する |
以下でそれぞれのフェーズの組織の壁について、解説していきます。
【30人の壁】創業メンバー中心の「集団」から「組織」へ
事象:阿吽の呼吸が通じない、理念がブレ始める
従業員が30人を超え始めると、これまで「言わなくても分かる」はずだった仲間意識に、少しずつズレが生じ始めます。
創業期の一体感が失われ、ささいな連携ミスやコミュニケーションロスが頻発するようになります。
これは、社長の目が物理的に全社員に行き届かなくなる最初のシグナルです。新しいメンバーは「指示が曖昧で動きづらい」と感じ、創業メンバーは「昔はもっと一体感があった」と不満を漏らす。
この段階で重要なのは、属人的な関係性に依存した「集団」から、共通の目的を持つ「組織」へと変化させることです。
打ち手①【経営者】:ビジョンを言語化し、語り続ける
このフェーズの経営者に求められるのは、なぜ自分たちがこの事業を行うのか、どこを目指しているのかという「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」を明確に言語化し、自分の言葉で、繰り返し、情熱を持って語り続けることです。
カルチャーは雰囲気ではありません。「こういう場面ではこう考え、こう動く」という統一された行動様式そのものです。
明確なビジョンこそが、社員が自律的に判断するための揺るぎない指針となります。
打ち手②【人事/マネージャー】:採用基準とオンボーディングを仕組み化する
組織の拡大を急ぐあまり、採用基準が曖昧になっていませんか?
スキルや経験だけで採用した結果、カルチャーに合わずに早期離職されてしまうのは、双方にとって不幸な結果を招きます。この段階では、MVVに共感し、体現してくれる人材かを見極めるための「採用基準」を言語化することが急務です。
そして、採用して終わりではありません。新しく加わった仲間が一日も早く組織に馴染み、パフォーマンスを発揮できるよう、入社後の受け入れプロセス(オンボーディング)を仕組み化し、会社全体でサポートする体制を構築しましょう。
よくある失敗談:いきなり完璧な評価制度を導入してしまう
30人の壁に直面した経営者が陥りがちなのが、「管理しなければ」という焦りから、大企業を真似た複雑で完璧な評価制度を導入してしまうことです。
しかし、この段階で管理コストの高い制度は、かえって現場の疲弊を招き、チャレンジ精神を削いでしまいます。
まずは評価制度の前に、MVVに基づいたシンプルな行動指針を全社で共有し、「何をすれば称賛されるのか」を明確にすることから始めるべきです。評価は後からついてきます。
【50人の壁】経営陣の"分身"となるミドルマネージャーの育成
事象:社長の目が届かず、部門間の連携が機能不全に
従業員が50人規模になると、社長一人が全社員の顔と名前を一致させ、全ての業務を把握することは物理的に不可能になります。
各部門は専門性を高めていきますが、その一方で「サイロ化」が進み、部門間の連携は滞り、セクショナリズムが蔓延し始めます。
「部下の評価基準が曖昧で困る」「新人のフォローが追いつかない」などの現場マネージャーからの声も頻繁に上がるようになります。
この壁を越える鍵は、経営者の"分身"となるミドルマネージャーの育成と、彼らが機能する仕組みづくりにあります。
打ち手①【経営者】:権限移譲と失敗の許容
多くの創業社長は、自身がトッププレイヤーであるため、無意識のうちに現場の細かい部分まで口を出す「マイクロマネジメント」に陥りがちです。
しかし、それではミドルマネージャーは育ちません。このフェーズで経営者が最も勇気をもって取り組むべきは、部下を信じて大胆に権限を移譲することです。
もちろん、任せた結果、失敗することもあるでしょう。しかし、その失敗を許容し、責任は自分が取るという姿勢を見せることで、マネージャーは挑戦し、成長していくのです。
プレイングマネージャーから脱却し、未来のリーダーを育てることにこそ、経営者は時間を投資すべきです。
打ち手②【人事】:次世代リーダーの発掘と育成
「うちにはマネージャーを任せられる人材がいない」と嘆く前に、次世代のリーダー候補を発掘し、育成する仕組みを構築することが人事の重要な役割です。プレイヤーとしては優秀でも、マネジメントに悩む人材は少なくありません。
彼らが壁を乗り越えられるよう、1on1ミーティングの導入支援や、マネジメント研修の機会を提供しましょう。
大切なのは、単発の研修で終わらせるのではなく、現場での実践とフィードバックを繰り返す継続的な育成のサイクルを回すことです。
打ち手③【マネージャー】:"言う"だけのティーチングから"聞く"コーチングへ
プレイヤーとして成功体験を持つマネージャーほど、「自分のやり方が正しい」と考え、部下に答えを教える「ティーチング」に偏りがちです。
しかし、それでは部下は指示待ち人間になるばかり。チームのパフォーマンスを最大化するためには、部下の考えや意見に耳を傾け、彼ら自身に答えを見つけさせる「コーチング」のアプローチが不可欠です。
定期的な1on1ミーティングの場で、部下のキャリアプランや悩みに真摯に向き合い、彼らの主体性を引き出す伴走者となることが、これからのマネージャーに求められる役割です。
よくある失敗談:外部から「優秀人材」を連れてきて丸投げする
マネジメント層の不足を補うために、外部から華々しい経歴を持つ「優秀人材」を採用するケースがあります。
しかし、これが組織崩壊の引き金になることも少なくありません。特に危険なのは、会社のカルチャーや歴史への理解・共感がないまま、その人物に過度な期待を寄せ、オンボーディングをおざなりにしてしまうことです。
彼らが持ち込む「一般的な正論」は、一見すると合理的ですが、その会社が大切にしてきた独自の価値観を破壊し、既存社員との間に深刻な軋轢を生む可能性があります。採用の際は、スキルや実績以上に、カルチャーフィットを最優先で考えるべきです。
【100人の壁】プロフェッショナル集団を動かす「仕組み」の構築
事象:情報が断片化し、組織の一体感が失われる
従業員数が100名を超えると、組織はさらに複雑化し、部門や役職を越えたコミュニケーションは著しく困難になります。
「誰が、どこで、何をしているのか分からない」「隣の部署が何で評価されているのか知らない」といった状態は、情報の断片化を招き、かつての一体感を失わせます。
多くの企業がこの段階でカルチャーの希薄化という深刻な問題に直面します。
この壁を乗り越えるには、個人の頑張りに依存するのではなく、組織全体を動かす公平で透明性のある「仕組み」を構築することが不可欠です。
打ち手①【経営者/人事】:MVVを体現する人事制度(評価・等級・報酬)の設計
これまで曖昧だった評価基準や給与決定のプロセスを見直し、MVVに基づいた公平で透明性の高い人事制度(評価・等級・報酬)を設計するタイミングです。
重要なのは、単に業績目標の達成度だけでなく、「会社のバリューに沿った行動が取れているか」を評価の根幹に据えることです。
どのような行動が称賛され、評価に繋がるのかを明確に示すことで、社員は日々の業務の中で自然とMVVを意識するようになります。
制度は社員を管理するためのものではなく、社員の成長を促し、カルチャーを体現するための羅針盤であるべきです。
打ち手②【全社】:情報の透明性を高め、部門の壁を壊す
意図的にコミュニケーションの機会を設計し、情報の透明性を高める努力が求められます。
全社員が集まる総会で経営状況やビジョンを共有する、社内報で各部署の取り組みや活躍する社員を紹介する、オープンなコミュニケーションツールを導入するなど、具体的な施策を通じて部門の壁を取り払いましょう。
社内の情報共有の活発さは、従業員のエンゲージメントや生産性に直結するという調査データもあります。
風通しの良い組織文化を「仕組み」として維持することが、100人を超えても成長し続ける企業の共通点です。
よくある失敗談:制度が「管理」のためのツールになってしまう
100人の壁を越えるために導入した人事制度が、いつの間にか社員の成長を促す目的を忘れ、単なる「管理」のためのツールと化してしまうことがあります。
細かすぎる評価項目、煩雑な申請フロー、減点方式の評価などは、社員から主体性やチャレンジ精神を奪い、エンゲージメントを著しく低下させます。
制度を導入する際は、常に「この仕組みは何のためにあるのか?」という目的を問い続け、形骸化させない努力が必要です。
まとめ:組織の壁は、会社が成長している証
本記事では、30人、50人、100人という企業の成長フェーズで訪れる「組織の壁」について、その原因と、経営者・人事・マネージャーそれぞれの立場からの具体的な打ち手を解説してきました。
30人の壁は、ビジョンを言語化し、「集団」から「組織」へ変化するフェーズ。
50人の壁は、権限移譲を進め、経営者の"分身"となるミドルマネージャーを育成するフェーズ。
100人の壁は、MVVを体現する「仕組み」を構築し、組織の一体感を再醸成するフェーズ。
今、組織の壁に悩み、この記事を読んでいるということは、それだけ会社が順調に成長している証拠に他なりません。大切なのは、その兆候を見逃さず、組織を次のフェーズへとアップデートしていくことです。
我々マネディクは、急成長ベンチャーが直面する組織課題、特に「管理職育成」の領域で、多くの企業をご支援してきました。もし、あなたが「次世代リーダーの育成に課題を感じている」「マネージャーの育成方法がわからない」といった悩みを抱えているなら、お力になれるかと思います。
具体的なサービスとしては、「マネジメントの内製化を目指した管理職研修」「スキルマップ」「カルチャー浸透ワークショップ」「離職防止のためのキーマンコーチング」などベンチャーや急成長企業特有の課題を解決するためのサービスをご用意しております。
少しでもご興味いただけましたら、以下リンクからサービス資料の無料ダウンロードをし、ご検討いただければ幸いです。